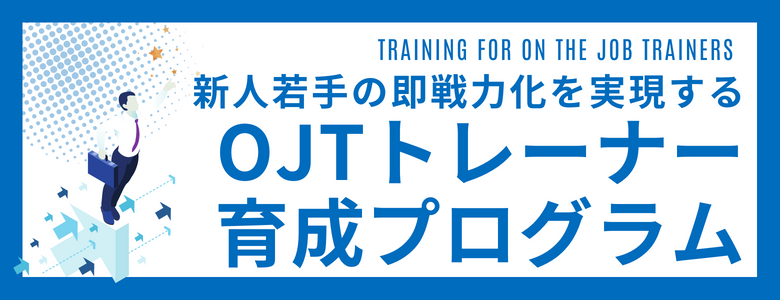OJT研修とは?進め方・成功のコツ・企業事例まで徹底解説!
新入社員や若手社員の育成方法として、多くの企業で取り入れられている「OJT研修」。本記事では、OJT研修の基本から、進め方の具体的ステップ、成功のポイント、さらに有名企業の導入事例までを網羅的に解説します。記事を読み終える頃には、自社に合ったOJTの設計方法や、即実践できるノウハウが手に入るはずです。これからOJTを導入する企業はもちろん、すでに実施しているが「効果が見えない」と感じている方も、ぜひ参考にしてください。
OJT研修とは?基本を理解しよう
OJT(On-the-Job Training)の意味
OJTとはOn-the-Job Trainingの略称であり、日常の仕事を通じて必要な知識・技術・技能・態度などを身につけられるよう、意図的・計画的に指導することを指します。企業内で行われる能力開発方法の1つであり、主として新入社員や若手を対象に制度化している企業が多いです。
OJTの目的は、新人の定着と戦力化の促進や早期離職の防止、OJTを担う若手~中堅社員やマネージャーの育成、共に学ぶ育成風土の醸成などが挙げられます。基本的に上司や先輩社員がマンツーマンで指導役となり、サポートしながら実務を行うことでスキルやノウハウを着実に身につけていきます。業務への自信をつけることで、新入社員の不安払拭や職場への定着促進も期待できるのです。
Off-JTとの違い
OJTとよく比較されるものにOFF-JT(Off The Job Training)があります。両者には明確な違いがあり、それぞれ特徴が異なります。
OJTは実務の場で必要な知識やノウハウを実践形式で行うアウトプットが中心です。一方、OFF-JTはインプットが主となり、実務の場を一時的に離れてのセミナーや研修で成長を促します。
OFF-JTの実践例としては、新入社員向けのビジネスマナー指導や、ベテラン社員が専門的スキルを身につけるための集合研修などが挙げられます。講師を招いた講座開催や、通信教育、eラーニングもOFF-JTのカテゴリーに当てはまります。以下に簡単に違いをまとめてみましょう。
【OJT・OFF-JTの違い】
指導者・指導形式:
OJT:先輩社員(OJTトレーナー)による実戦形式の指導
OFF-JT:外部講師・ベテラン社員などによる講義・セミナー形式の指導
教育できる内容:
OJT:実務の遂行に必要なスキルを学べる(アウトプットが中心)
OFF-JT:普遍的かつ汎用的なスキルを学べる(インプットが中心)
指導対象:
OJT:トレーナー1名に対してトレーニー1名でおこなわれる
OFF-JT:複数名の参加者を対象におこなわれる
厚生労働省の令和4年度能力開発基本調査では、正社員に対する教育訓練としてOFF-JTを実施している企業は70.4%でした。多くの企業が正社員に対する教育訓練としてOJTも実施している現状を考えると、実務的な教育が可能なOJTも、業務環境から離れて体系的に知識を学べるOFF-JTも、どちらも重要視されていることがわかります。
効果的な人材育成のためには、OJTとOFF-JTどちらか一方ではなく、両方をバランスよく活用し、自社のニーズと照らし合わせながら使い分けていくことが重要です。
なぜOJTが注目されているのか
社内リソースを活用できる
OJT研修の目的として、研修コストを抑えることも挙げられます。産労総合研究所の「2021年度 教育研修費用の実態調査」によると、従業員1人あたりの教育研修費用は24,000円〜50,000円程度で推移しています。
人材育成において投資対効果を高めるためには、研修効果を高める工夫と共に、費用を抑えることが重要です。OJT研修は外部の研修サービスやプログラムを利用するよりも費用を抑えられるため、育成の投資対効果を高める手段として注目されています。ただし、コストのみを優先すると本来期待するスキルが得られない可能性もあるため、育成目的を明確にした研修設計が必要です。
若手定着・即戦力化への期待
OJTの目的としてまず挙げられるのは、トレーニーの職務遂行能力向上です。これはトレーニーの成長意欲や自己実現意欲の満足にもつながります。年功序列や終身雇用が変化する中、新入社員に早期から仕事への責任意識を持たせることができ、能力と意欲を高めることで組織への順応促進と人材定着につながる期待が大きいのです。
リーダー育成の場にもなる
指導役となるOJTトレーナー自身の能力向上も図れます。効果的なOJT実施によって、トレーナーは周囲からの信頼を得ることができます。組織としても社員の指導力向上を通じて次世代リーダー育成に役立て、一定以上のスキルを持った状態で育成をスタートできるという利点があります。
OJT研修のメリット・デメリット
OJT研修のメリット
個別対応が可能
OJTはトレーナーと1対1で指導が受けられるため、新人の個性や強みを把握しやすい関係の構築が可能です。それぞれの「できること」「できないこと」をベースに、目標設定やオリジナルの育成計画を立案し、新人のレベルに合わせた教育のカスタマイズが実現します。他の新人についていけない社員がいても、その社員のペースに合わせた指導が行えるため、多様な人材の育成に適しています。
コミュニケーションの深化
OJTは新人に即戦力をつけさせることで活躍のチャンスが広がり、モチベーション維持に寄与し、職場への定着率アップにつながります。上司や先輩社員が一人と向き合い指導できるため、個人の強みや弱みを把握しやすく、社員同士のコミュニケーションがとりやすい関係性を構築できます。これにより丁寧なサポートや配慮をしながら仕事を進められ、新入社員のバーンアウトやエンゲージメント低下も防止できます。
外部研修だけでは実務に則した知識やスキルの習得が難しく、外部講師雇用や会場準備などのコストも発生します。一方、OJTは内の上司や先輩が指導するため、コスト面の負担が少なく、1対1の熱量の高い教育体制が実現できます。
業務理解の促進
OJTでは上司や先輩社員からの指導を受けながら、新人自身が試行錯誤し、実地に基づいた教育ができるため、効率的な即戦力の育成が可能です。座学主体の研修は体系的知識の習得には役立ちますが、実際に活用できるレベルに定着させるためには実務経験が不可欠です。OJTは明確な目的をもったステップを踏んでトレーニングするため、経験やスキルの定着力が強く、学びを着実に蓄積しながら成長できます。
OJT研修のデメリットと注意点
教える側の負担が大きい
OJTの大きなデメリットは、教える側の業務負荷が増加することです。OJTトレーナーは自分の業務を行いながら新人育成・指導に当たるため、時間的にも身体的にも負担が増えます。自分の評価は通常の業務結果で判断されるため、OJTと本来業務の両立が求められ、余裕がなくなると新人を放置してしまう事態も発生しがちです。
教えるスキルが必要
OJTがうまくいかない原因の一つに、トレーナーの指導スキルと管理スキルの不足があります。現場では必ずしも教える経験が豊富で優れたスキルを持った人材がトレーナーになるとは限りません。また、適切なフィードバックが行われないと、新人は成長を実感できずモチベーションが下がってしまいます。
株式会社LDcubeの2023年調査によれば、OJTトレーナー研修を「社内講師で実施」は37%、「外部講師で実施」は9%、「実施していない」が45%という結果でした。OJTを効果的に機能させるためには、トレーナー育成の仕組みづくりが欠かせません。
属人的になりやすい
OJTの最大のデメリットは「ばらつき」が生じやすいことです。OJTは先輩社員のスキルや経験に大きく依存するため、教え方や伝え方が不十分だと新人のスキルアップが困難になります。異なるトレーナーから指導を受けると、教える側のばらつきにより、教えられる側の社員間でスキルや知識習得にも差が生じてしまいます。
トレーナー研修などでばらつきを軽減する施策を行っても、完全になくすことは難しいのが現実です。このばらつきを最小限に抑えることができれば、人材育成の効果は大幅に改善できるでしょう。
OJT研修の成功に必要な3つの要素
① 計画性(ゴールとステップ)
OJT設計書や計画表の作成方法
OJTには「意図的」「計画的」「継続的」の3つの原則があります。OJTを実施するにあたっては、まず目的を明確にし、「どの社員を対象にし、どのように育成するために実施するのか」を考えることが必要です。対象となる社員の選出基準も設定しておきましょう。たとえば、「新入社員の即戦力化」が目的なら、新卒社員に限るのか中途社員も含むのかを決めておく必要があります。
OJTは指導役の能力によって教育の質にムラができやすいため、事前に計画書を作成することが重要です。計画書には育成目標や対象者の現スキルレベル、目指すレベルを記載し、日別の研修内容や指導役の所感欄も設けます。策定した指導計画に沿って実施すれば、ムラなく効率的な指導ができるでしょう。
スキルマップとの連携
さらに、OJTをスキルマップと連携させることも効果的です。スキルマップを導入する最大のメリットは、企業内の「スキルギャップ」を埋められることです。スキルギャップとは、企業のビジョン実現に必要なスキルと従業員が持つスキルの隔たりを指します。育成計画を立てたら、「OJTリーダーが業務をやってみせる→意味や背景を説明する→新入社員にやってもらう→フィードバックを行う」というステップを繰り返し実施しましょう。
② コミュニケーションと信頼関係
教える側と教わる側の関係構築
会社はチームプレイであり、メンバー間のコミュニケーションが不可欠です。特に新人や後輩には「報告・連絡・相談(ホウレンソウ)」の重要性を教えましょう。「報告」は仕事の経過や結果を上司へ伝えること、「連絡」は情報を関係者へ伝えること、「相談」は助言をもらうことです。ホウレンソウを小まめに行うことで、お互いの距離が縮まり、OJTリーダーの業務負荷も軽減できます。
フィードバックの質を高めるには
入社したばかりの頃はやる気に満ちていても、次第にモチベーションを失うケースもあります。その原因の一つがOJTリーダーの指導法にあります。失敗した新人に対して、きちんと話を聞かずに怒ってしまうと相手を萎縮させてしまいます。どんなときでも相手の話に耳を傾け、主体性を持たせることが大切です。また、設定した目標をしっかり共有し、達成度を定期的に確認しながら励ましていくことで、新入社員のやる気を高められるでしょう。
③ 評価と振り返り
OJTの効果測定方法
育成目標や計画について上司と合意
業務の結果やプロセスに対する具体的な評価・指導がOJT研修の効果を高めます。心理学の分野では「褒める」と「叱る」の割合は5:1が適切とされており、ポジティブなフィードバックを心がけることが重要です。
そして、OJTの終了後は、設定した目標に対する達成度合いを測定・評価する必要性があります。具体的には、策定した計画書に基づいて下記項目を測定します。
- 実際に習得したスキルや知識を評価
- 目標達成にかかった期間を集計
- 目標達成度合いを総合的に評価
これは学習者の自己評価だけでなく、OJTトレーナーや上司の評価も交えて多角的に行うことが大切です。評価結果は学習者にフィードバックし、改善点や課題を今後のOJTに役立てましょう。
継続的な改善フロー
OJT研修ではPDCAサイクルを意識することも重要です。
Plan:実現したいゴール、スキル、育成計画を立てる
Do:目標に向けてOJT研修を実施する
Check:スキルの習得度合いを把握し、フィードバックを行う
Action:フィードバックに基づき研修を修正・再開する
「意図的」「計画的」「継続的」の3原則を踏まえ、定期面談を含め、状況に応じて最適な方法を模索することで、OJT研修の効果を最大化できるでしょう。
具体的なOJT研修の進め方(4ステップ)
ステップ①:準備と目標設定
学習者のレベルを見極める
効果的なOJT研修は「Show」「Tell」「Do」「Check」の手順に沿って進めることが重要です。まず準備段階として、学習者のレベルを見極め、適切な目標設定を行いましょう。
一人ひとりの現状を把握することは、OJTの設計や内容を最適化するうえで非常に重要です。そのためには、配属前や研修初期に面談の機会を設けることが効果的です。
面談では持っている知識やスキル、これまでの環境や経験、どのような不安を感じているのかといった背景や状況を丁寧にヒアリングしましょう。このステップが、現場で求められる水準と、個々のスタート地点との差を明確にしてくれます。
特に、業種や職種の違い、入社前の経験の有無により、習得スピードや課題が異なります。画一的な指導ではなく、多様な状況を踏まえた柔軟な対応が求められるのです。現場での気づきや学びを深めるには、学習者の「今」を知ることから始めるのが鉄則です。
研修設計のフレームを作成
OJTを効果的に進めるには、事前に計画書を作成することが不可欠です。策定した指導計画に沿ってOJTを実施すれば、ムラなく効率的な指導ができます。計画書には育成目標、現時点でのスキルレベル、OJT終了時に目指すレベル、日別の研修内容、指導役の所感記入欄などを設けましょう。
重要なのは、トレーナーだけに育成を任せるのではなく、組織全体で取り組む姿勢です。OJTの進め方や指導方法を現場やトレーナーに丸投げせず、経営層や人事部も関与して全社的に進める必要があります。会社の目的や目標に合った人材育成のために経営層も積極的に関わり、企業全体がポジティブに人材育成に取り組める環境づくりが、OJTの効果的な運用につながります。
ステップ②:説明と模範
見せて学ばせる
STEP1.<Show>やってみせる
OJT研修の最初の工程は、これから教える業務を担当者がやってみせて全体像を理解してもらうことです。口頭説明だけでは具体的にイメージできないため、実際に電話をかける、パソコンを使って作業するなど、手本を見せましょう。
STEP2.<Tell>説明・解説する
続いて、見せた業務について詳しく説明します。ただ流れを説明するだけでなく、なぜこの手順で作業したのか、どうしてこの作業を行うのかなど、目的や背景まで理解してもらうことが大切です。こまめに不明点や疑問点がないか確認しましょう。
OJT研修による学習効果を高めるには、手本を見せてわかりやすく解説することが重要です。シチュエーショナルリーダーシップの考え方では、「励ます」「任せる」「正す」「教える」の4つがありますが、OJT研修は多くの場合「教える」に分類されるため、しっかりと手本を見せて教える手順を踏むことを意識しましょう。
コツや失敗例もセットで伝える
また、業務の内容だけでなく、コツや失敗例もセットで伝えることが効果的です。とりわけZ世代は、業務を行う意義をきちんと伝えるとモチベーションが保ちやすくなります。業務の全体像や必要性を把握することで、イレギュラーがあっても臨機応変に対応できるようになります。
ステップ③:実践とフォロー
実務への投入タイミング
STEP3.<Do>やらせてみる
業務の説明・解説を終えたら、実際にその業務をさせてみましょう。これにより、本当に理解できているかどうかが確認できます。慣れるまでは放置せずに見守ることが大切です。Z世代は失敗を強く恐れる傾向があるため、いきなり難しい業務ではなく、簡単なタスクから始めて徐々にステップアップしていくと良いでしょう。
OJT研修の実施には、段階的なアプローチが効果的です:
観察(See):研修生は指導者の業務遂行を注意深く観察し、その場で解説を受ける
実践(Do):基本的な作業から着手し、適切なサポートとこまめなフィードバックを受ける
応用(Practice):より複雑な業務に挑戦し、問題解決力の向上と独自の工夫を促す
自立(Master):完全な戦力として独り立ちし、他者への指導や業務改善の提案も期待される
フィードバックと励まし
実践段階では、適切なフォローも重要です。コーチングとティーチングを使い分け、本人の主体性を引き出しながら指導しましょう。また、メンタルケアも忘れてはいけません。特に新入社員や若手社員は心理的安全性を感じられないとストレスが蓄積し、学習効果が低下します。日々のコミュニケーションの中で悩みを聞く機会を設けることが大切です。
ステップ④:振り返りと評価
振り返り面談の方法
STEP4.<Check>評価・指導する
実践した業務について、フィードバックを行います。できていなかった点を指摘するだけでなく、うまくできていた点を褒めることも重要です。
できていなかった点については、「どうして失敗が起きたのか」「今後同じことが発生したとき、どうすれば改善するのか」「今後同じことが起きないようにするにはどうすればいいか」を具体的に解説することが必要です。そして、現時点での評価をもとに今後の指導計画を立て、目標のレベルに達するまで「Show」から「Check」までのサイクルを繰り返します。
学びを定着させるために、デイヴィッド・A・コルブが提唱した経験学習モデル(「経験」「省察」「概念化」「実践」のサイクル)を活用することも効果的です。心理学の分野では、「褒める」と「叱る」の割合は5:1が適切とされています。ポジティブなフィードバックとネガティブなフィードバックのバランスに気をつけましょう。
定期的な進捗評価は以下の観点から行うと良いでしょう:
- 設定目標の達成度
- スキル習得の度合い
- 業務遂行の質と速度
評価方法としては、客観的な指標による測定、自己評価とのギャップ分析、周囲からの評価収集などがあります。
次へのステップを提示
成功した場合は褒めた上で、よりよい結果を出すにはどうすべきかを考えさせると効果的です。Z世代は承認欲求が強い傾向があるため、よい点は具体的な言葉で積極的に褒めるようにしましょう。今までの成功・失敗体験の多さを問わず、失敗した場合も叱責するのではなく、原因や改善策を一緒に考え、次のステップへと導くことが大切です。
OJTトレーナーに必要なスキルとマインド

育成する力(コーチング・ティーチング)
教え方の型(ティーチング)
ティーチングとは、答えを与える形で学習者に必要な知識やスキルを教えることを指します。OJTトレーナーから学習者に状況に応じて必要な情報を伝える必要があるため、OJTトレーナー自身が仕事の知識やスキル、意味や目的の整理ができる他、分かりやすく物事を伝えるコミュニケーション能力を磨くこともできます。
気づかせる力(コーチング)
コーチングは、ティーチングスキルのように学習者に答えを予め教えるのではなく、相手の考えを、傾聴と問いかけによって引き出し、自ら答えを導き出せるように働きかけます。OJTトレーナーがコーチングスキルを習得し、コーチング主体でOJTを実施することで新入社員の自律性や自己解決能力を養いやすくなります。細かな指示や指導を行うのではなく、コーチングを通じて新入社員が自主的にアクションを起こせるように適切にサポートすることで、自己成長や自主性を高めることができるでしょう。
観察力と状況判断力
「見る」ではなく「観る」
学習者は指導者の業務遂行を注意深く観察します。この段階で重要なのは、単なる見学に終わらせないことです。業務の流れやポイントについて、その場で解説を加えることで、より深い理解を促します。
OJTトレーナーは、褒めたり、叱ったり、フィードバックを行ったりしながら育成を行いますが、そのときに欠かせないのが相手の変化に気づくこと。そして「●●のやり方を変えたんだね。今の対応すごく良かったよ!」といったようにその場で声をかけることが大事です。
また特に入社して間もない期間は知らず知らずのうちにストレスを感じやすいものです。「あれ?いつもと違うな」と何か兆しに気付いたら、「どうしたの?」と声をかけるといいでしょう。当然、相手が安心して話ができるような関係性も重要ですし、話してくれたら「言ってくれてありがとう」と伝えるなど受け止めることも大事になってきます。
状況に応じた対応力
OJTトレーナーは教え方だけではなく、褒め方や叱り方など、学習者の出した成果に対する適切なコミュニケーションの心得があることも重要です。適切に褒めたり叱ったりすることで、新入社員のモチベーションを維持向上させ、より効果的に自己成長を促しやすくなります。褒める際には具体的な部分を褒め、叱る際には感情的になるのではなく、具体的に改善点を伝える必要があるため、状況に応じた柔軟なコミュニケーション能力が必要になるでしょう。
心理的安全性の確保
質問しやすい雰囲気づくり
OJTでは教える側、教わる側の関係性が大事になってきます。良い関係を築くためには、相手の長所も短所も、その人自身の個性だと考えて認めて受け入れることが重要です。そしてOJTトレーナーは、自分自身の完璧ではない部分を認め、それも含めて相手と向き合うのがいいでしょう。完璧すぎると取っつきにくくなりがちで、不完全な部分を感じられると親近感がわくものです。
その上で、「やれば必ずできる」と相手を信じて向き合い続ける根気や相手への配慮、気配りが大事になってきます。
「失敗しても大丈夫」という文化
OJTでは、学習者の成長プロセスに根気強く寄り添う心構えが求められます。人の成長には個人差があり、同じことを教えても習得のスピードや理解の深さは異なります。
何度教えても習得できていない場合でも、焦らず丁寧に指導を続けることが大切です。特に、業務の基本となる知識やスキルは、繰り返し教え、確実に身に付けさせる必要があります。「一度教えたから分かっているはず」という思い込みは禁物です。
また、成長の過程では停滞期や壁にぶつかる時期も必ず訪れます。そのような時こそ、OJTトレーナーの励ましや支援が重要になります。学習者の様子をよく観察し、困っている様子があれば声をかけ、必要に応じてアドバイスや励ましの言葉をかけましょう。一時的な停滞に過度に反応せず、長期的な視点で成長を見守る姿勢が重要です。
OJT研修がうまくいっている企業事例
事例①:スターバックスジャパンのOJT
「サードプレイス」として多くの人に愛され続けるスターバックス。その成功の裏には、業界の常識を大きく覆すOJT研修があります。一般的な飲食業界では2~3日で済ませることが多いOJTを、同社では驚きの80時間かけて実施しているのです。
最も特徴的なのは、技術習得よりも企業理念の浸透に重点を置いていることでしょう。「コーヒーを売る仕事ではなく、コーヒーを通じて人を喜ばせる仕事」という考え方を、アルバイトから正社員まで全スタッフが共有できるまで徹底的に教え込みます。この価値観の共有こそが、マニュアルに頼らない質の高いサービスを生み出す源泉となっているのです。
指導方法も独創的です。失敗を指摘するのではなく、うまくいった場面で「なぜ成功したのか」を本人に考えさせ、ポジティブな行動パターンを定着させていきます。この「成功の理由を自分で分析する」プロセスが、スタッフの自主性と創造性を育んでいるのです。
結果として、80時間の研修を終えたスタッフは、画一的なサービスではなく、一人ひとりが状況に応じて考え抜いたおもてなしを提供できるようになります。これこそが、スターバックスが世界中で愛される理由の一つといえるでしょう。
事例②:ニコン株式会社のOJT
精密機器メーカーとして高い技術力を誇るニコン。同社のOJT研修は、製造業における人材育成のお手本として注目を集めています。
最大の特徴は、OFF-JTとOJTを効果的に組み合わせた体系的なプログラム設計です。まず1年間かけて事業理解からIT基礎まで幅広い知識を座学で習得し、その後実務に入るという流れになっています。この事前準備があることで、配属後のOJTでは即座に実践的な学びへと移行できるのです。
現場でのOJTでは、新入社員一人に対して必ず一人の先輩がトレーナーとして付き、マンツーマンで指導を行います。そして研修の集大成として「OJT成果プレゼンテーション」を実施し、学んだ内容を言語化・体系化させることで知識の定着を図っています。
この段階的なアプローチにより、複雑な技術や知識も確実に継承され、新入社員は配属から短期間で戦力として活躍できるようになります。製造業特有の高度な技術習得を、無理なく着実に進められる仕組みといえるでしょう。
事例③:マルハニチロのOJT
食品業界大手のマルハニチロが実践するのは、「みんなで育てる」を合言葉にした、職場全体参加型のOJTです。
同社では「OJTリーダー」と呼ばれる先輩社員が新入社員の専属指導者となりますが、その役割は業務指導にとどまりません。目標設定から日常の悩み相談まで、新入社員のあらゆる不安に寄り添う「メンター」としての機能も担っているのです。
さらに注目すべきは、OJTリーダー一人に責任を押し付けるのではなく、部署全体で新人を支える文化を築いていることです。加えて、個人の成長ペースに合わせたOFF-JT研修も柔軟に組み合わせることで、一人ひとりに最適化された育成プログラムを提供しています。この手厚いサポート体制により、新入社員の早期定着と戦力化を実現しているのです。
OJTをより効果的にするための工夫
Off-JTとの組み合わせ
事前学習やeラーニングとの連動
「OJTとOff-JT、どちらが効果的なのか?」という議論をよく耳にしますが、これは的外れな問いです。重要なのは、それぞれの強みを活かしながら戦略的に組み合わせることなのです。
現代の人材育成において注目されているのが「ブレンディッドラーニング」という考え方です。これは、体系的な知識習得が得意なOff-JTと、実践的なスキル定着に優れたOJTを、まるでカクテルのように絶妙に調合する手法といえるでしょう。
多くの企業で見られる失敗例が、「とりあえずやってみよう」という姿勢で新人をいきなり現場に放り込むことです。マニュアルを渡して「頑張って」と言うだけでは、新人は全体像を掴めないまま迷走してしまいます。これは、地図を持たずに知らない街を歩き回るようなものです。
効果的なアプローチは、まずOff-JTで業務の全体像と基礎知識をしっかりと習得させることから始まります。この段階でeラーニングを活用すれば、時間と場所の制約を受けずに効率的な学習が可能になります。特に動画教材は視覚的理解を促進し、個人のペースに合わせた反復学習を実現します。
基礎固めが完了したら、今度はOJTの出番です。ここでは、事前に習得した知識を実際の業務場面でアウトプットし、理論と実践の橋渡しを行います。現場で起こる予期せぬ問題や複雑な状況への対応力は、この段階で初めて身につくのです。
そして、基本業務が安定したら再びOff-JTに戻り、より高度な知識やスキルを学習する。このようなスパイラル学習により、継続的な成長が実現されます。このサイクルこそが、変化の激しい現代ビジネス環境で求められる「学び続ける力」を育成する鍵となるのです。
OJT設計ツールの活用
OJT計画テンプレート
優れたOJT計画書は、単なる書類ではありません。それは、育成担当者と新入社員が共有する「成長への道筋」なのです。
効果的な計画書には、対象者の基本情報から始まり、明確な育成期間、具体的な目標設定、段階的な育成項目、詳細なスケジュール、多様な指導方法、客観的な評価基準まで、すべてが網羅されています。これらの要素が有機的に連携することで、迷いのない育成プロセスが構築されるのです。
特に重要なのは、育成項目に優先順位をつけることです。すべてを同時に教えようとすれば、新人は情報過多で混乱してしまいます。「まず何を」「次に何を」「最終的に何を」という明確な順序が、効率的な学習を促進します。
スキルチェックリスト
人材育成の大きな課題の一つが、個人差への対応です。同じ研修を受けても、理解度や習得速度は人によって大きく異なります。
スキル管理ツールは、この個人差を「見える化」する強力な武器です。一人ひとりの強み、弱み、学習ペース、特性などを詳細に記録し、データに基づいた個別最適化された指導を可能にします。これにより、画一的な指導から脱却し、真にパーソナライズされたOJTが実現されるのです。
DX時代のOJT(リモート・動画活用)
リモートOJTの成功条件
コロナ禍を契機として急速に普及したリモートワーク。しかし、従来のOJT手法をそのままオンラインに移植しただけでは、期待される効果は得られません。デジタル環境特有の課題を理解し、それに適応した新しいアプローチが必要なのです。
オンライン環境での最大の課題は、コミュニケーション不足です。対面であれば自然に生まれる何気ない会話や、表情から読み取れる微細な変化が、画面越しでは伝わりにくくなります。この課題を解決する3つの黄金法則があります。
まず「高頻度接触」です。量的に減ったコミュニケーションを、接触頻度を上げることで補完します。毎日の朝夕ミーティングで、短時間でも確実にコンタクトを取ることが重要です。
次に「短時間集中」です。オンライン疲労を考慮し、一回あたりの接触時間を15分程度に設定します。短時間だからこそ、密度の濃いやり取りが可能になるのです。
最後に「双方向意識」です。一方的な情報伝達ではなく、新人からの発信を促す仕組みを意識的に作ります。役割分担を明確にし、全員が発言しやすい環境を整備することが肝要です。
録画教材で再学習を促す
Z世代の学習スタイルを考慮すれば、動画活用は必然の流れです。YouTubeで学ぶことが当たり前の世代に、従来の紙ベースのマニュアルを押し付けても効果は限定的でしょう。
動画教材の最大のメリットは「品質の標準化」です。教える人によって内容がブレることなく、いつでも誰でも同じ品質の教育を受けられます。また、繰り返し視聴による自己ペース学習が可能で、理解が不十分な部分は何度でも確認できます。
さらに、質問しづらい若手の心理的負担も軽減されます。「これ、前にも聞いたかな?」という不安を感じることなく、必要に応じて何度でも学習し直せる環境は、心理的安全性の確保にも寄与するのです。
これらの工夫を組み合わせることで、従来の枠を超えた効果的なOJTが実現できます。重要なのは、新しいツールや手法に振り回されるのではなく、本質的な人材育成の目的を見失わないことです。テクノロジーは手段であり、目的ではないのですから。
OJT研修を成功させるために今すぐできることを実施しよう
効果的なOJT研修を実現するためには、まず「OJTの位置づけを明確にする」ことが重要です。OJTは単なる業務の伝達ではなく、企業理念の浸透や組織文化の継承、さらには新入社員の成長を促す重要な機会です。スターバックスのように、80時間をかけて基本理念から徹底的に学ぶ姿勢は、OJTの本質を表しています。自社において、OJTがどのような役割を果たすべきか、明確なビジョンを持ちましょう。
次に、「トレーナーへの教育も忘れずに」実施することが欠かせません。どれだけ素晴らしいOJT計画を立てても、それを実行するトレーナーのスキルが不足していては効果が半減します。ティーチングとコーチングの使い分け、適切な観察力と状況判断力、心理的安全性を確保する能力など、OJTトレーナーに必要なスキルとマインドを育成する研修を設けましょう。特に、最近増えているリモート環境でのOJTでは、高頻度・短時間・双方向のコミュニケーションが重要になります。
さらに、「OJTのPDCAを定着させよう」という意識も大切です。OJT計画書やスキルチェックリストなどのツールを活用し、育成の進捗を可視化しましょう。定期的に振り返りの機会を設け、うまくいっている点と改善すべき点を明確にします。Off-JTとの効果的な組み合わせや、動画などのデジタルツールの活用も検討し、常に改善を続けることがOJTの質を高めます。
これらの取り組みを通じて、新入社員の成長を支援するだけでなく、指導する側も成長できる環境を整えることができます。「職場全体で育てる」という意識を持ち、組織の一体感を醸成しながら、一人ひとりの成長を促す。それがOJT研修成功の鍵となるでしょう。今日から、あなたの職場でもできることから始めてみませんか?
ワークハピネスが提供しているOJTトレーナー研修
私どもは、新入社員の配属の時期も踏まえつつ、短時間の研修を数回に分けながらインプットと職場実践を繰り返すアクションラーニング形式でも良いですし、1日の研修でしっかり学び切る形式でも良いと考えています。
ワークハピネスのOJTトレーナー研修の内容についてはこちらをご覧ください。

人材アウトソーシングのベンチャー企業㈱エスプール(ワークハピネスの親会社)の創立3年目に新卒にて入社。新規現場、プロジェクトの立ち上げから不採算支店を売上日本一の支店に再生するなど、同社の株式上場に貢献してきた。
多数のプロジェクトを通じ、多くのスタッフと携わる中で「人間の無限の可能性」を知り、「人の強みを活かすマネジメント」を広めるべく、2006年よりワークハピネスに参画。
中小企業を中心とした人材開発、組織風土変革コンサルティングPJを推進している。