
現場で成果を生む人材マネジメントの実践ガイド — 信頼・動機づけ・チーム成果を高める手法
現代は、企業の成果が「人」で決まる時代です。管理職だけでなく、チームを率いるリーダーや中堅社員にも「人を動かす力」が求められる昨今では、現場での人材マネジメントがますます重要になっています。
しかし実際には、「指導がうまくいかない」「部下との関係が築けない」といった課題を抱える現場も少なくありません。
本記事では、人材マネジメントの意味や基本スキル、実務での活用法から、部下育成・チームづくり・評価・エンゲージメント向上の具体例まで紹介します。日々の業務の中で人を育て、成果を生み出すためのヒントを見ていきましょう。
人材マネジメントとは?定義とビジネス現場での役割

人材マネジメントは、従来の「管理」という概念を超えた、現代的なアプローチです。まずは人材マネジメントの定義や現場での役割を確認しましょう。
「マネジメント=管理」ではない
多くの人は「マネジメント」と聞くと、部下を監視し、指示に従わせることをイメージしがちです。しかし人材マネジメントは、一人ひとりの能力と意欲を最大限に引き出し、自律的な行動を促すことを目的としています。
現代の人材マネジメントは、権威による支配ではなく、信頼と尊重に基づく関係性の構築を重視します。メンバーを「管理される対象」ではなく、「協働するパートナー」として捉え、それぞれの強みを活かしながら組織目標の達成を図るのです。
組織目標とメンバーの成長を両立する“人を動かす技術”
効果的な人材マネジメントの核心は、組織の目標達成と個人の成長を、同時に実現することにあります。短期的な組織の成果のみを追求すれば、メンバーは疲弊し、持続可能な成長は望めません。逆に個人の成長のみに注力すれば、組織としての結束力や目標達成力が低下する可能性があります。
メンバーが自らの成長を実感しながら組織に貢献できる環境を作ることで、内発的なモチベーションが向上し、持続可能な高いパフォーマンスを維持することができます。
管理職だけでなく、現場リーダーにも求められる視点
現代のビジネス現場では、正式な管理職の立場にない人々にも、マネジメント的な視点と能力が強く求められています。プロジェクトリーダーやチームリーダー、先輩社員など、さまざまな立場の人が「人を動かす力」を必要としているのです。
こうした役割の人は、命令や指示による統制ではなく、影響力や説得力、調整力を通じてチームを導かなくてはなりません。
ビジネスの現場では、年齢や経験に関係なく、その時々の状況や専門性に応じて、誰もがリーダーシップを発揮する機会があります。全てのメンバーが基本的なマネジメントスキルを身につけておくことが、組織全体の効率性と効果性を向上させる鍵となるのです。
なぜ職場で対立が起きるのか
たくさんの人が働く現場では、意見の食い違いや価値観の対立が起こります。ここではトラブル未然に防ぎ、スムーズな人間関係を目指すために、職場で起きる対立の要因や課題をまとめました。
よくある対立の原因
職場での対立の多くは、メンバー間の価値観の違いから生まれます。最も顕著なものは、世代間ギャップです。異なる時代背景で育った世代は、仕事やキャリアに対する価値観、コミュニケーションスタイルなどが大きく異なります。
また個人の価値観や性格の違いも、対立の要因のひとつです。コミュニケーション不足から情報の伝達ミスや認識のズレが起き、当事者の意図に関係なく、深刻な誤解や不信感を生み出すこともあります。リモートワークなどの多様な働き方が普及する現代、コミュニケーション不足は、多くの組織が抱える課題のひとつです。
潜在的対立と顕在化した衝突の違い
対立には、段階があります。潜在的対立は、不満や緊張が存在するものの、まだ表面的には問題として認識されていない、または公然と表現されていない状態です。
一方、顕在化した衝突は、対立が明確に表面化し、関係者全員が問題の存在を認識している状態です。感情的な対立が生じることも多く、場合によっては、当事者間の関係性に深刻な損傷が生じています。
顕在化した衝突の解決には、より多くの時間と労力を要し、場合によっては第三者の介入や組織的な対応が必要です。
早い段階で適切に対処することで、大きな問題への発展を防ぐことができます。
対立が起こる背景にある組織課題
職場の対立は、組織的な課題が根本原因となっていることが少なくありません。
特に誰がどの業務に責任を持つのか、意思決定の権限はどこにあるのかが曖昧な場合、メンバー間で責任の押し付け合いや権限争いが生じやすくなります。
また役割の重複や空白地帯が存在すると、非効率性や混乱が生まれ、対立の原因となります。
不適切な評価制度も対立を引き起こします。個人の成果のみを重視し、協力やチームワークを適切に評価しない制度では、メンバー間の競争が過度になり、協調性が失われます。またリソースの不足や配分の不公平、不適切なリーダーシップスタイルも、対立を助長する要因となります。
まずは組織内の課題を洗い出し、根本的な対立の解消を目指しましょう。
マネジメントが必要とされる理由と背景
人間関係のトラブルやチーム全体の課題の解決には、専門的なマネジメントが有効です。次はマネジメントが必要とされる理由や時代的な背景を見ていきましょう。
なぜ「個」の力だけでは限界なのか
業務が複雑になり、グローバル化によって考慮すべき要因が多様化した昨今、現場には、さまざまな方面への専門性が求められています。こうした状況への対応には、一人の担当者だけでは困難です。
さらにイノベーション創出には、異なる視点や専門性を持つ人々の協働が不可欠です。つまり現代のビジネス現場は、多様なスキルや価値観を持つ人が互いに協力し、分担しあうことで成り立っているのです。
変化の激しい時代における“チーム成果”の重要性
チームによる成果創出の最大の利点は、相乗効果が得られることです。個人の能力の足し算ではなく、それぞれの能力を活かすことで、より大きな成果を目指すことが可能になります。
またリスクが分散できることも、チームのメリットのひとつです。重要な意思決定や戦略立案を複数の人間で行うことで、個人の判断ミスや認識の偏りによるリスクを軽減できます。さらに業務の属人化を防ぐことで、組織の持続性を確保することも可能になります。
チームでの作業は大きな力を生む一方、個人と個人の関係性を取り持つためには全体のマネジメントが必要になります。個の力を最大限に発揮し、チームとしての成果を上げるために、マネジメントが役立つのです。
多様性・リモートワーク時代に必要な“関係性構築”
働き方や働く人が多様化し、現代のビジネス現場には、さまざまな背景を持つ人が集まっています。多様化した組織では、従来の「同質性」を前提とした関係性構築は機能しません。また、物理的な距離により、「偶発的な交流」に依存した関係性構築も困難になっています。
特にリモートワーク環境では、物理的な近接性に依存した関係性構築が不可能になります。デジタルコミュニケーションでは、非言語的な情報が少なくなり、細かな感情やニュアンスの伝達が困難です。
さらに異なる時間帯で働くメンバーや、家庭の事情で制約のあるメンバーとの関係性構築には、従来以上の配慮と工夫が必要です。多様性の利点を生かすためにも、人材マネジメントを活用した取組が役に立ちます。
人材マネジメントに欠かせない3つの力
人材マネジメントでは、「関係性構築力」「動機づけ・エンパワーメントの力」「状況判断と意思決定の力」が必要です。
ここでは人材マネジメントに欠かせない3つの力を解説します。
関係性構築力
関係性構築力は、人材マネジメントのすべての活動の基盤となる能力です。
信頼関係を構築するには、まず継続的で、一貫した行動を示すことが大事です。約束を守る、言動に一貫性を保つといった基本的な行動の積み重ねが、徐々に信頼関係を育んでいきます。
また相手の立場や状況を理解し、配慮する姿勢も求められます。メンバーの立場や感情を理解し、それに適切に対応する共感力も、信頼関係の構築に役立ちます。
良好な関係性を築く能力は、チームをまとめ、適切な人材配置を行うためにも、不可欠な能力なのです。
動機づけ・エンパワーメントの力
効果的な動機づけのためには、まず個人の価値観や目標を理解しましょう。メンバーが何を大切にし、どのような将来を描いているのかを知ることで、それを組織目標と結びつける方法を見つけることができます。仕事の意味づけは、労働の動機づけの重要な要素です。
またエンパワーメントとは、メンバーに適切な権限と責任を委譲し、自己決定の機会を拡大することです。メンバーが自分で判断し、行動できる範囲を広げることで、責任感と達成感を醸成することができます。
成長機会の創出と挑戦的な目標設定によって、メンバーは自分の限界を超える経験を積みます。能力の向上だけでなく、自発的な成長をうながすことにもつながるのです。
状況判断と意思決定の力
適切な状況判断と意思決定を行うには、情報の収集と分析能力が必要です。必要な情報を効率的に収集して信頼性と関連性を評価し、意思決定に活用できる形で整理する力が求められます。
またリスクを回避し、優先順位を正しく判断することも必要です。まずリスクを正しく認識し、影響度と発生確率を評価します。そして組織の目標達成に向けて、受容可能なリスクを判断しましょう。
さらにチーム運営における状況判断と意思決定では、メンバーの能力や状況に応じたタスクの割り当てやサポートのタイミングを決めることも重要な要素のひとつです。人間関係や感情面を考慮した人間的な判断を行うことで、より効果的なチーム運営が可能になります。
急速に変化するビジネス環境に対応するためには、従来の判断力や意思決定力だけでは不十分です。リスキリングやDX人材育成といった新しいテーマを組織に取り入れ、変化に適応できる人材を育てていくことも、人材マネジメントに求められる重要な要素となっています。
メンバーの特性に応じたマネジメント手法
多様な人材が集まるチームでは、メンバーの特性に合わせたマネジメントが求められます。特性ごとのアプローチのポイントをまとめました。
世代別・経験別のマネジメントアプローチ
世代や経験の違いは、仕事に対する価値観や動機づけの要因に大きな影響を与えます。まずは世代ごとの特徴を把握したうえで、アプローチしましょう。
ベテラン社員に対するマネジメントでは、これまでの経験や知識を尊重し、それを活かせる役割や責任を与えるのがおすすめです。
中堅社員は、しばしば上司と部下の板挟みになる立場にあり、ストレスを感じやすい傾向があります。適切なサポートと相談の機会を提供し、困難な状況に対処するための支援を行いましょう。
若手社員に対しては、基本的なスキルの習得と職場適応を支援しながら、自主性と創造性を育む環境を用意しましょう。定期的なフィードバックを通じて成長を実感させ、キャリア目標の設定と達成を支援することで、長期的なエンゲージメントを維持できます。
Z世代へのマネジメントのポイント
Z世代の多くは、仕事に対して目的意識を強く求める傾向があります。業務の背景や目的を明確に説明し、その仕事が組織や社会にどのような価値をもたらすのかを示しましょう。
また働き方に対する価値観も大きく異なります。ワークライフバランスを重視し、柔軟な働き方を当然の権利として考えるのです。リモートワークやフレックスタイム、副業などの多様な働き方を受け入れ、個人の価値観やライフスタイルに応じた働き方を支援することが、この世代の能力を最大限に引き出すことにつながります。
さらにプロジェクト管理ツールやオンライン学習プラットフォームなどのデジタルツールを積極的に活用することで、より効率的で快適に働けるようになります。
パーソナライズされた関わり方とは?
マネジメントでは、メンバーの性格特性や学習スタイル、コミュニケーション嗜好、キャリア志向などを把握し、それに応じたアプローチを取ることが重要です。同じチーム内であっても、同じ手法が、全ての人に効果的であるとは限りません。個人の特性に合わせた環境づくりが必要です。
学習スタイルの違いも重要な考慮要素です。視覚的学習が得意な人には図表やチャートを活用した説明を、体験的に学習するタイプの人には、実際に手を動かす機会を提供しましょう。
定期的な1on1ミーティングや非公式な対話を通じて、メンバーの変化や成長、新しいニーズや関心事を把握し、それに応じてアプローチを調整してください。
マネジメント現場で起こる課題とその対処法
実際にマネジメントを行っている現場では、すでにいくつかの課題が見えてきているかもしれません。ここでは、マネジメント現場が抱えやすい課題や対処法を見ていきましょう。
指示が通らない、チームがまとまらない
指示が通らない主な原因には、コミュニケーションの不備が挙げられます。指示の内容が曖昧で理解しにくかったり、相手の理解度を確認せずに一方的に伝えていたりすると、相手は言われたとおりのタスクをこなせません。
また「言っていることがコロコロ変わる」と思われると、新しい指示に対しても消極的な態度を取ることがあります。まずはチーム内の信頼関係を見直し、指示には一貫性を持たせましょう。例外的な指示では、その理由を伝えることも重要です。
チーム全体の業務の流れや到達点が見えないと、メンバーはまとまりません。目標はシンプルに、わかりやすく伝え、自分たちの業務がどう影響しているのかわかるようにしておきましょう。
評価のすれ違いやモチベーションにばらつきがある
何を基準に評価されるのかが明確でない場合、メンバーは自分なりの基準で成果を判断しようとします。その結果、上司の評価と食い違いが生じるのです。
評価プロセスの透明性不足も、モチベーションの低下につながります。評価基準はできるだけ明確に定め、特に数値で測れる部分ははっきりと明示するなど、メリハリのある開示を行いましょう。
さらに成長実感の有無も、モチベーションのばらつきに影響します。すべてのメンバーが成長を実感できるように、小さな評価を積み重ねましょう。
信頼関係が築けないときの対処は?
信頼関係が築けない状況は、マネジメントにおいて最も困難な課題のひとつ。信頼関係構築の第一歩は、自己の行動を客観的に振り返ることです。
約束を守っているか、一貫した態度を取っているか、透明性のあるコミュニケーションを心がけているかなど、信頼される行動を継続的に実践しているかを確認しましょう。
自分だけでは解決が困難な状況では、外部の専門家やメンターからのアドバイスを求めることも有効です。客観的な視点からの助言によって、自分では気づかなかった問題点や改善方法を発見できるかもしれません。
外部の研修も積極的に取り入れ、新しい考え方を身につけましょう。
効果的なマネジメントに役立つツールと制度
効果的なマネジメントでは、ツールや制度を有効に活用することが大切です。マネジメントの現場でよく使われる、ツールや制度を確認していきましょう。
1on1ミーティング
1on1ミーティングは、上司と部下が定期的に行う個別面談です。現代のマネジメントでは、一般的なツールのひとつ。従来の評価面談とは異なり、部下の成長支援と関係性構築を主目的とした継続的なコミュニケーションの場として位置づけられます。
1on1ミーティングを成功させるためには、上司側のスキル向上も重要です。傾聴スキル、質問スキル、フィードバックスキル、コーチングスキルなどを身につけることで、より質の高い1on1を実施することができます。また、部下との信頼関係構築や、心理的安全性の確保も重要な要素です。
エンゲージメントサーベイ
エンゲージメントサーベイは、従業員の組織に対する愛着度や貢献意欲を定期的に測定するツールです。定量的なデータによって組織の状況を客観的に把握し、改善点を特定しましょう。
重要なのは、サーベイの結果を踏まえた具体的な改善アクションを取ることです。上位の課題について優先順位をつけ、実行可能な改善計画を策定し、責任者と期限を明確にして実行します。問題が早期発見できれば、深刻化する前に対処することも可能になります。
タレントマネジメントシステム(TMS)
タレントマネジメントシステム(TMS)は、従業員の能力、経験、実績、キャリア志向などの情報を一元管理し、人材配置、育成計画、後継者計画などに活用するシステムです。人材情報の可視化により、戦略的な人材活用と育成投資の最適化を図ることができます。
個人の成長履歴やポテンシャルを可視化し、適材適所の配置や個別の育成計画策定が可能になるのです。
これらのツールは単独で使用するよりも、相互に連携させることでより大きな効果を発揮します。
成功事例:マネジメント改革でチームが変わった企業たち
人材マネジメントの理論を学んでも、実際の現場で成果を上げるには実践的なアプローチが不可欠です。ここでは、マネジメント改革によって劇的な変化を遂げた企業の成功事例を紹介します。
ケース1:1on1導入で離職率30%改善
ある企業では、優秀な人材の突然の離職が続いていました。「評価もしているし、重要な仕事も任せているのに、なぜ辞めるのか分からない」という管理職の声が多く、人事部では原因の特定に苦慮していました。
同社が導入したのは、上司と部下が定期的に1対1で対話を行う1on1ミーティングです。
導入にあたって、管理職は傾聴スキルやコーチング手法の研修で部下自身が答えを見つけられるよう質問で導くアプローチを習得。コミュニケーションの質が大きく向上しました。
その結果、離職率は大幅に改善され、従業員エンゲージメントスコアも向上しました。
ケース2:評価制度の再設計で中堅社員の定着化
中堅社員の離職と成長停滞感が課題となっていた企業では、従来の年功序列的な評価制度によって、勤続年数の長い社員から不満が噴出していました。
そこで同企業では評価制度を根本から見直し、透明性と成長支援を重視した新しい仕組みを構築しました。
さらに定期的な進捗面談の実施と360度評価を導入し、多角的な視点からの評価を実現。成長支援計画を上司と部下で共同作成する仕組みを整えました。
改革によって中堅社員の離職率は大幅に改善され、従業員満足度調査でも評価制度に対する満足度が大きく向上しました。
ケース3:心理的安全性を高めたリーダー育成事例
この企業では、組織が大きくなる中で「会議で誰も発言しない」「新しいアイデアが出てこない」「失敗を恐れて挑戦しない」といった問題が顕在化していました。
同社は心理的安全性の向上に着目し、リーダーシップ変革プログラムを開始しました。リーダーが自身の失敗談を共有したり、メンバーの意見を積極的に求めたりすることで、組織の心理的安全性が大きく向上したのです。
また失敗を隠すのではなく、学習機会として活用する文化が根付き、リスクを取った挑戦が増えることで新サービスの開発スピードも向上しました。
人材マネジメントを強化するための第一歩
人材マネジメントの改革を成功させるには、まず自社の現状を正確に把握することから始めましょう。また経営層が人材マネジメントの重要性を理解し、長期的な視点でコミットすることが不可欠です。
さらに近年は、上場企業を中心に「人的資本開示」への対応も求められています。自社の人材マネジメントの取り組みを定量的・定性的に示すことは、経営戦略を強化するうえで重要なポイントとなるでしょう。
そして最も重要なのは、「信頼関係を築く」ことです。日々の小さなコミュニケーションの積み重ねから、マネジメントの基盤となる関係性を構築していくことが、すべての改革の出発点となります。
自社内だけで人材マネジメントを強化するのが難しいと感じたときは、ワークハピネスにご相談ください。貴社の課題にあわせた研修をカスタマイズし、人材マネジメント力の向上をお手伝いいたします。
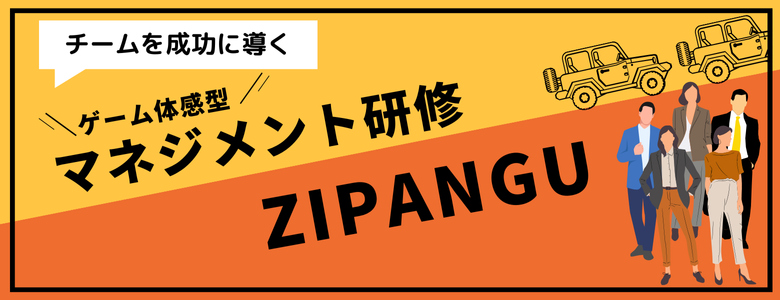
ワークハピネスのゲーム体験型マネジメント研修「ZIPANGU」では、管理職が押さえておくべき基本的なマネジメントの考え方を身につけ、自分のチームに何ができるかを明確なアクションとしてアウトプットします。
ゲームで起きたことを振り返りながら、エンゲージメントが高まる、チームのパフォーマンスが高まっていく働きかけはどのようなものだったのかを学ぶことができます。そして、学んだ内容を現実でどのように実践していくかを研修の中で具体化します。研修前後の仕組みとともに、確実な行動変容に繋げることができます。
ゲーム体験型マネジメント研修「ZIPANGU」サービスページはこちら
研修資料ダウンロード
ワークハピネスの研修は、ゲームで実践する、座学より効率的に効果を上げられる研修を提供しています。

大学卒業後、外資系医療機器メーカーで営業に従事。
6年間で8人の上司のマネジメントを経験し、「マネジャー次第で組織は変わる」と確信し、キャリアチェンジを決意する。
2009年にワークハピネスに参画し、チェンジ・エージェントとなる。
医療メーカーや住宅メーカーをはじめ、主に大企業の案件を得意とする。また、新人から管理職まで幅広い研修に対応。
営業、営業企画、新人コンサルタント教育を担当後、マーケティング責任者となる。
一度ワークハピネスを退職したが、2021年から復帰し、当社初の出戻り社員となる。現在は、執行役員 マーケティング本部長。























