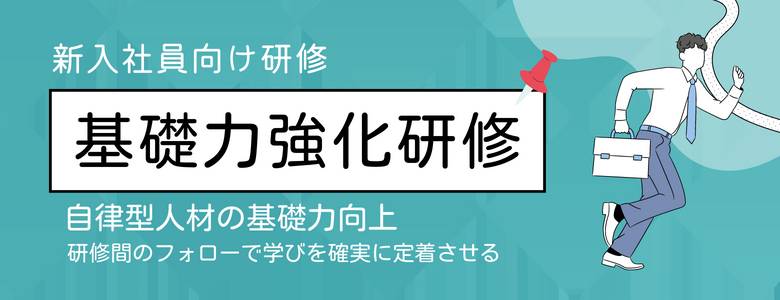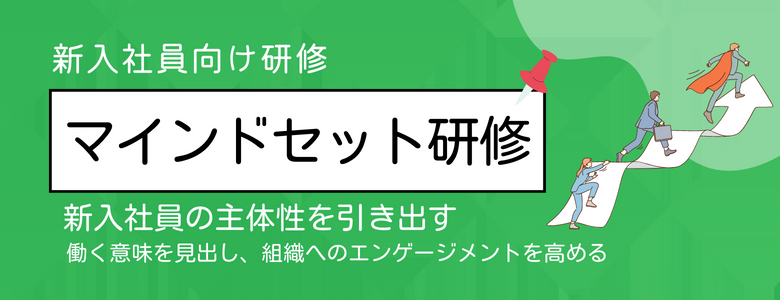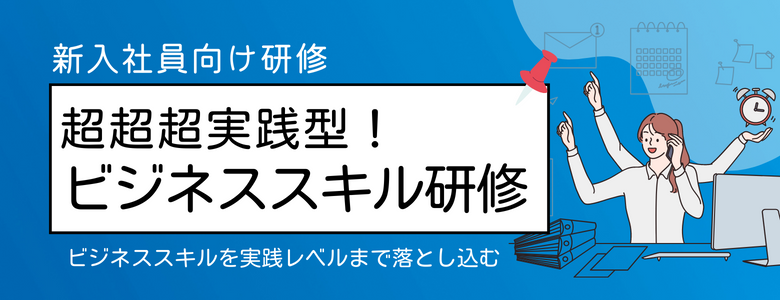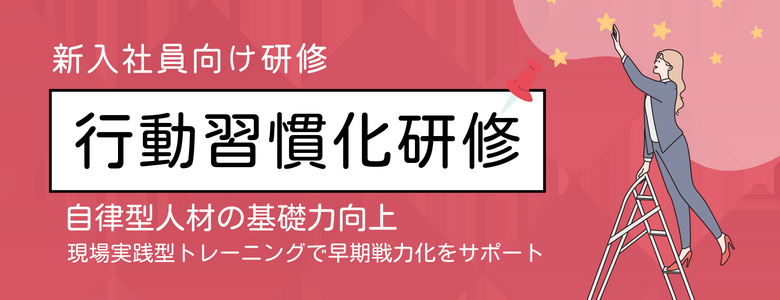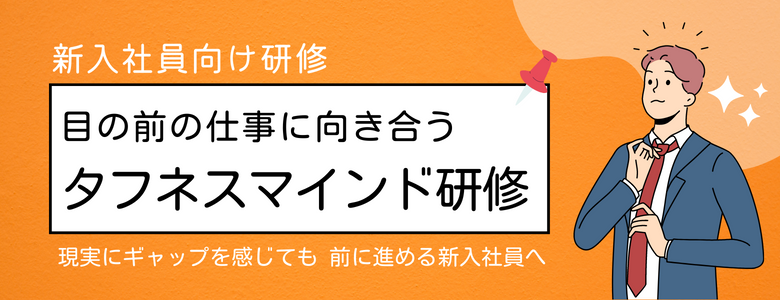2年目研修とは?目的・内容・職種別カリキュラム・レポート例まで徹底解説【2025年最新版】
社会人2年目は、仕事にも慣れつつ「責任」と「主体性」が求められる転換期です。
その節目に実施される「2年目研修」は、1年目の振り返りを通じて成長課題を明確化し、次のステップへ進むための重要な機会となります。
本記事では、2年目研修の目的・内容・テーマ・職種別カリキュラム(研修医・教員・看護師・保育士など)、さらにレポートや感想の書き方、服装や当日の注意点までわかりやすく解説します。2025年最新版として、企業・公務員・医療・教育などあらゆる業界で役立つ構成でまとめました。
2年目研修とは? ― 社会人の転換期に必要なステップ

入社2年目は、社会人としての“土台づくり”を終え、次のステージへと進む重要な時期です。
1年目のように「教えられる立場」から、「自ら考え行動する立場」へと変化することで、責任感や主体性が求められます。この転換期に行われる「2年目研修」は、社会人としての成長を再確認し、今後のキャリアを主体的に描くための大切な機会です。
フォローアップ研修や3年目研修と並び、離職防止・モチベーション維持にも効果を発揮します。
社会人・入社2年目の立ち位置と求められる役割
入社2年目は、基礎業務を一通り経験し、周囲から「即戦力」としての成果を期待される段階です。
上司や先輩のサポートを受けつつも、自分自身で課題を見つけ、改善へとつなげる行動力が求められます。
一方で、1年目のようなサポート体制が薄れるため、「自信の喪失」や「目標の喪失」に陥りやすい時期でもあります。
そのため、2年目研修では次のようなテーマが重視されます。
- 自己理解の深化(強み・弱みの再確認)
- 業務の質を高めるためのタイムマネジメント
- 後輩指導・チーム貢献への意識醸成
- モチベーション維持とキャリアの方向性明確化
これらを通して、「自分が組織にどのように貢献できるか」を明確にし、主体的な行動を促すのが狙いです。
「2年目研修」「フォローアップ研修」の目的と背景
2年目研修は、入社後の実務経験を踏まえて「振り返りと再出発」を行う位置づけにあります。
特に以下のような背景から、多くの企業が実施しています。
- 1年目のフォローアップ研修では主に「定着支援」が目的だったが、
2年目研修では「成長促進」と「自立支援」が目的に変わる。 - 社会人生活に慣れ、マンネリ化しやすい時期に“学び直し”によって再び成長意欲を高める“学び直し”を行うことで、再び成長意欲を高める。
- 組織としても、若手社員の離職率を下げ、次世代リーダー候補の育成を早期に始めたいという意図がある。
このように、2年目研修は単なる「おさらい」ではなく、キャリアの節目を意識させる再スタート研修の意味合いを持ちます。
「2年目3年目研修」との違い・位置づけ
2年目研修と3年目研修は混同されやすいですが、目的と効果は明確に異なります。
| 項目 | 2年目研修 | 3年目研修 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 自立・主体性の強化 | リーダーシップ・後輩指導力の育成 |
| 対象層 | 一通りの業務を覚えた若手社員 | チームを任され始めた中堅層 |
| 研修内容 | 目標設定・自己分析・モチベーション管理 | 指導・育成・チームマネジメント |
| タイミング | 一般的な傾向として入社2年目(春〜夏) | 一般的な傾向として入社3年目(秋〜冬) |
つまり、2年目研修は“個人としての土台づくり”が中心であり、3年目以降の“リーダー的成長”へつなぐステップとなります。
研修を行う主な目的(早期離職防止・モチベーション維持・主体性強化)
① 早期離職の防止
入社1〜3年目の離職率が高いといわれる中、2年目研修は“中だるみ”の防止に効果的です。
「自分の成長が見えない」「将来像が描けない」といった不安を解消することで、キャリア継続への意欲を高めます。
② モチベーション維持とキャリア意識の再構築
仕事に慣れ、成果や評価が求められ始める時期だからこそ、「なぜこの仕事を選んだのか」「今後どんな自分になりたいか」を見つめ直す機会が必要です。
2年目研修では、内省ワークやキャリアデザイン演習などを通じて、再び“やりがい”を実感できるよう支援します。
③ 主体性・自律性の強化
これまで「指示を受けて動く」立場から、「自ら提案・実行する」立場へと移行するために、主体性を鍛えるプログラムが組まれます。
グループワークやケーススタディを通じ、リーダーシップの基礎やチーム貢献の重要性を体感的に学びます。
2年目研修の目的と期待される効果
入社2年目は、社会人としての“成長曲線の分かれ道”といわれる時期です。
1年目で基本的な業務を覚えた後、「自ら考え、動く力」が問われ始めます。
このタイミングで実施される2年目研修は、単なるスキルアップではなく、プロ意識・主体性・チーム貢献・生産性向上・キャリア再設計といった、社会人としての総合力を育むことを目的としています。
以下では、その具体的な5つの目的と、企業・本人双方にとっての効果を詳しく解説します。
目的① プロ意識と責任感を育てる
2年目社員には、「一人前」としての意識が強く求められます。
1年目は“教えてもらう立場”でしたが、2年目からは“任される立場”へと変化します。
研修では、仕事に対する姿勢やミスへの責任の持ち方、成果へのこだわりなど、プロとしての意識改革が中心テーマとなります。
具体的には次のような効果が期待されます。
- 指示待ちからの脱却(自分で考え、動ける意識の形成)
- 責任をもって成果を出すための行動力向上
- 「チームの一員」としての役割理解の深化
これにより、「自分の仕事が会社全体にどう影響するか」を俯瞰的に捉えられるようになり、仕事へのモチベーションが安定します。
目的② 主体的に考え行動できる「自走力」の強化
入社2年目で最も重要とされるのが“自走力”です。
上司の指示を待つのではなく、自ら課題を見つけ、解決に向けて動ける人材が求められます。
研修では、ロジカルシンキングや課題解決ワークなどを通して、自ら考え行動するための思考プロセスを学びます。
また、振り返り(リフレクション)や成功体験の共有により、「自分で考え行動できた経験」を可視化し、再現性を高めます。
この過程で、モチベーション維持と成果創出の両立が可能になります。
目的③ チーム貢献・コミュニケーション能力の向上
社会人2年目になると、後輩の指導やチーム内連携の機会が増えます。
そのため、協働力や伝達力の強化は欠かせません。
研修では、グループワークやロールプレイを通して、次のような能力を育みます。
- 意見の伝え方・聞き方・折衝スキル
- チーム内での報連相(報告・連絡・相談)の精度向上
- 後輩や同期へのサポート意識の醸成
単なる「個の成果」ではなく、「チーム全体の成果」に貢献できる人材へと成長することが目的です。
これにより、リーダーシップの基礎力も自然と身につき、将来的なマネジメント層育成の第一歩となります。
目的④ 生産性・業務効率アップ(段取り・タイムマネジメント)
業務に慣れてくる2年目だからこそ、次に必要なのは「効率的に仕事を進める力」です。
段取り力・優先順位判断・時間管理などのスキルが成果を左右します。
研修では、次のような内容が扱われます。
- タスクの整理・優先順位付けの方法
- 納期を意識したスケジュール設計
- 集中力を高めるための環境・思考整理法
こうしたトレーニングにより、「がむしゃらに頑張る」から「計画的に成果を出す」働き方へと変化します。
結果として、生産性向上・残業削減・ストレス軽減といった効果が見込めます。
目的⑤ 自己理解・キャリアビジョンの再構築
2年目は、将来への迷いやキャリアの方向性に悩み始める時期でもあります。
そのため、研修では自己理解を深め、キャリアの再設計を行うことが重視されます。
具体的には、以下のようなワークが取り入れられます。
- 自己分析(価値観・強み・成長課題の棚卸し)
- 5年後・10年後のキャリアビジョン作成
- キャリアアンカー診断や目標設定ワーク
これにより、自分の「得意」「やりがい」「目指す姿」が明確になり、仕事への納得感が高まります。
結果として、離職防止・モチベーション維持・成長意欲の向上という好循環が生まれます。
2年目研修の内容・カリキュラム例
2年目研修では、「知識の習得」よりも「実践力の強化」が主な目的となります。
1年目で培った基礎をもとに、自立・主体性・チーム貢献を高めるための内容が多く組まれます。
カリキュラムは大きく分けて
①振り返り ②役割理解 ③実践スキルの習得 ④定着フォロー
という4段階で構成されるのが一般的です。
全体の構成(振り返り → 役割理解 → 実践スキル)
2年目研修の多くは、次のような流れで設計されています。
| ステップ | 主な内容 | 目的 |
|---|---|---|
| STEP1:自己振り返り | 1年目の経験を棚卸し、成長点と課題を整理 | 自己理解と課題認識 |
| STEP2:役割理解 | 組織の中で求められる役割や期待を再確認 | プロ意識・責任感の醸成 |
| STEP3:実践スキル習得 | ロジカルシンキング・報連相・コミュニケーションなど | 主体性と実務力の強化 |
| STEP4:フォローアップ | 現場での実践計画・上司との面談・事後課題 | 学びの定着と行動変容 |
このように、研修は「内省 → 理解 → 実践 → 定着」の流れで構成され、
単発ではなく長期的な成長支援プログラムとして位置づけられています。
主要テーマ例
2年目研修では、業種・職種を問わず共通して次のようなテーマが扱われます。
それぞれのテーマの目的と進め方を具体的に見ていきましょう。
1年目の振り返りと成長課題の明確化
まず行われるのが「自己振り返り」です。
1年間の成功体験・失敗体験を整理し、自分の強み・弱みを客観的に見つめ直します。
- ワークシートを使った「行動の棚卸し」
- 成果につながった要因・課題の分析
- 同期同士での経験共有ディスカッション
このプロセスを通じて、自分が成長できた点と今後の改善点を明確化します。
感覚的な“頑張り”ではなく、“行動・結果・学び”をデータとして言語化することが目的です。
2年目としての目標設定と行動計画
振り返りを踏まえ、次に行うのが「今後1年間の行動計画づくり」です。
2年目研修では、単なる数値目標ではなく、“どう成長するか”というプロセス目標を設定します。
- SMART目標法(具体的・測定可能・達成可能・現実的・期限付き)
- 5W1Hを活用したアクションプランの策定
- 上司・人事との面談を通じた目標フィードバック
これにより、日々の行動とキャリア目標が結びつき、成長を「見える化」できます。
ロジカルシンキング・問題解決・報連相トレーニング
実務で成果を出すためには、「考える力」と「伝える力」が欠かせません。
そこで多くの2年目研修では、以下のような思考・伝達スキル系カリキュラムが取り入れられます。
- ロジカルシンキング(構造的に考えるトレーニング)
- 問題発見・解決のフレームワーク(MECE/ロジックツリー)
- 報連相(報告・連絡・相談)の実践演習
- ケーススタディ:上司・同僚・後輩との連携シミュレーション
このような実践演習を通じ、現場で即使える「考える×伝える力」を体得します。
グループワークを通じたコミュニケーション強化
2年目研修では、グループワークが中心的な要素となります。
同年代の社員同士が協働し、意見を出し合いながら課題に取り組むことで、チームワーク・傾聴・発言力を鍛えます。
主なワーク例:
- 他部署・他職種混合のグループディスカッション
- チーム課題(プレゼン発表・提案ワークなど)
- フィードバック演習(相互評価・改善提案)
こうした体験型学習を通じ、社内ネットワークの構築や視野の拡大にもつながります。
結果として、組織全体の連携力・協働意識の底上げが期待できます。
英語・専門スキルアップ(研修医/グローバル職対応)
業種によっては、2年目研修に専門スキルや語学研修が組み込まれることもあります。
特に医療・教育・グローバル企業では、以下のような内容が実施されます。
- 研修医:診療報告書作成・患者対応コミュニケーション・チーム医療演習
- 教員:授業設計・児童理解・学級運営スキル研修
- グローバル職:英語プレゼン・異文化コミュニケーション・ビジネス英語表現
このように、2年目研修は「職種に応じた専門性の深化」と「汎用スキルの強化」を両立させる構成になっています。
フォローアップ・事後課題・現場定着化の工夫
研修で学んだ内容を“現場で使える力”に変えるためには、事後フォローが不可欠です。
多くの企業では次のような仕組みを導入しています。
- 研修後レポートの提出(学び・行動宣言のまとめ)
- 上司面談によるフィードバック(研修内容の実践確認)
- 3か月後・半年後のフォローアップ研修(行動定着支援)
- 社内SNS・OJT連携による進捗共有
これらを組み合わせることで、「学ぶ → 実践 → 振り返る」サイクルが定着します。
結果として、短期的なモチベーション維持だけでなく、長期的なキャリア形成にもつながります。
職種別:2年目研修の実施例と特徴
2年目研修は、業界や職種によって目的や内容が大きく異なります。
共通するのは「1年目の振り返りと自立支援」という基本軸ですが、現場での役割・専門性・求められるスキルが異なるため、各業界ごとの特徴に合わせた研修設計が行われています。
ここでは、代表的な職種ごとの2年目研修の実施例と特徴を詳しく紹介します。
研修医の2年目研修
ローテーション・スケジュール・年収・バイト事情
医師臨床研修制度において、2年目は「研修医生活の集大成」と位置づけられます。
1年目で救急・内科・外科などの基本診療科を経験した後、2年目では選択科ローテーションを中心に、より専門性の高い実習が行われます。
- スケジュール例:多くの病院では4〜5科を数か月単位でローテーション(内科系・外科系・地域医療など)
- 年収の目安:厚生労働省「臨床病院における研修医の処遇」による調査(平成22年11月実施)では、研修医年収は概ね320〜720万円の範囲が相場とされている国公立病院で約450〜500万円、民間病院では500〜700万円前後が相場
- アルバイト(いわゆる「バイト」):2年目の後半から可能な施設もあるが、病院規定により制限があるため要確認
また、当直回数も増え、実践的な診療スキル・判断力が問われる段階に入ります。
研修医向けの2年目研修では、医療安全・チーム医療・リーダーシップ・医療倫理などが中心テーマになります。
試験・何科選択・英語・勉強・貯金・結婚・出産などの生活面
2年目の後半には、専門医コースや後期研修先を決める時期が訪れます。
どの科に進むか(内科・外科・皮膚科・精神科など)を考える上で、研修医同士の情報交換やOB訪問が重要になります。
- 試験:後期研修・専門医プログラムの筆記・面接対策
- 英語:国際学会発表・英語論文に備え、英語研修を取り入れる病院も増加
- 勉強時間:勤務後や休日にオンライン講座・勉強会を活用
- 貯金・結婚・出産:生活が安定し始める時期で、将来設計を意識する人も多い
このように、2年目研修医は“医師としての自立”と“人生設計のスタート”が同時に訪れる時期といえます。
教員・公務員の2年目研修
千葉県・鳥取県・大阪府など自治体ごとの傾向
教員や公務員の2年目研修は、**地方自治体(教育委員会や人事院)**が主体で実施しています。
たとえば、各都道府県では次のような特徴があります。
- 千葉県:「実践力・協働力」を重視し、授業改善や学級運営をテーマに年数回実施
- 鳥取県:「地域貢献型教員育成」を掲げ、地域教育・家庭連携の研修が多い
- 大阪府:「主体的な教育者像」を軸に、メンタルケアやチーム学校運営を重視
研修は1日〜数日間にわたり、講義・模擬授業・グループディスカッションを通じて行われます。
また、教員研修センターでは2年目対象の通信研修(eラーニング)も整備されています。
教職2年目研修のテーマとレポート例
教員の2年目研修では、次のようなテーマが中心です。
- 学級経営・児童理解・いじめ対応
- ICT活用・特別支援教育・授業改善
- チーム学校としての協働・保護者対応
レポート提出では、「授業改善計画」や「教育活動を通じた成長課題」などがテーマになることが多く、
例文としては以下のような形式が一般的です。
例文(抜粋)
「2年目に入り、児童一人ひとりの個性を理解し、柔軟に対応する力の重要性を実感しました。研修で学んだ“傾聴と承認”を意識した関わりを実践し、学級の雰囲気が改善しました。」
看護師・保育士の2年目研修
看護協会の研修制度と目的
看護師や保育士の2年目研修では、「新人卒業後の成長支援」がテーマです。
特に看護職では、日本看護協会や各病院の教育委員会が次のようなカリキュラムを設けています。
- 看護倫理・医療安全・感染対策の再確認
- リーダーシップ・プリセプター準備研修
- チーム医療・多職種連携演習
目的は、「自立した専門職としての判断力と協働力の育成」です。
2年目は新人指導を任されることも多く、“教える立場”への移行を支援する内容が増えます。
新人との関わり方・メンタルケア・チーム支援
2年目になると、後輩が入職してきます。
そのため、メンター的な立場としてのコミュニケーションスキルが求められます。
- 新人への声かけ・相談対応の方法
- チーム全体のメンタルサポートの仕組み
- ストレスマネジメント研修(燃え尽き防止)
特に医療・保育現場では、感情労働が大きいため、心身のセルフケアを学ぶ内容も多く導入されています。
一般企業・採用2年目・社会人全般
業界別(営業・IT・製造)のカリキュラム例
一般企業における2年目研修は、実務スキルとマインドの両面強化を目的に実施されます。
代表的な業界別のカリキュラム例は以下の通りです。
| 業界 | 主な内容 | 狙い |
|---|---|---|
| 営業職 | 顧客対応ロールプレイ・プレゼン演習・クレーム対応 | 提案力・交渉力・顧客満足度の向上 |
| IT職 | プロジェクト進行・チーム開発・リーダー準備研修 | 主体性・協働力・マネジメント意識の強化 |
| 製造業 | 品質管理・改善提案・安全教育 | 生産性・改善力・安全意識の定着 |
また、社内メンター制度やリーダー候補選抜研修と連動している企業も多く、2年目以降のキャリアパス形成の基盤になります。
2年目研修の服装・持ち物・休む際の注意点
服装は「スーツまたはオフィスカジュアル」が基本です。
企業によっては私服参加可の場合もありますが、清潔感・TPOを意識するのが原則です。
持ち物例:
- 筆記用具・ノート・社員証
- 事前課題・自己分析シート
- PCまたはタブレット(オンライン参加の場合)
欠席・遅刻の注意点:
やむを得ず休む場合は、上司・人事担当へ事前連絡を徹底し、事後フォロー(録画視聴・レポート提出)を行うのが一般的です。
研修は人事評価やキャリア支援の一環として扱われるため、誠実な対応が求められます。
2年目研修のレポート・感想・フォローアップの書き方
2年目研修の締めくくりとして多くの企業・自治体で求められるのが、「研修レポート」や「感想文」です。
これは単なる“感想記入”ではなく、自分の学びを言語化し、行動変化につなげるための重要なプロセスです。
さらに、研修後のフォローアップ(2年目フォロー研修)では、このレポートが行動計画の基盤となります。
以下では、目的別にレポート・感想・フォローアップの書き方と評価されるポイントを解説します。
研修レポートの目的と構成(例文付き)
■ レポートの目的
研修レポートの目的は、
- 研修で得た「学び」や「気づき」を整理する
- 今後の業務にどう活かすかを明確にする
- 上司・人事に「成長意欲」と「行動計画」を共有する
の3点にあります。
つまり、レポートは「学びの記録」ではなく、「行動宣言書」としての役割を持ちます。
■ レポートの基本構成
レポートの書き方は、以下の3部構成がわかりやすく、評価されやすい形式です。
| 構成 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| ① 研修で印象に残ったこと | 具体的な講義・ワーク・講師の言葉など | 「報連相の演習を通じて、自分の伝え方に無駄が多いことに気づいた。」 |
| ② そこから得た学び・気づき | 自分の行動や考え方にどんな変化があったか | 「相手の立場を意識することで、伝え方を変える重要性を実感した。」 |
| ③ 今後の実践計画・目標 | 学んだことを現場でどう活かすか | 「報告前に“目的・要点・期限”を整理して伝えることを徹底したい。」 |
■ レポート例文
例文(一般企業の場合)
「今回の研修で印象に残ったのは、“結果ではなくプロセスを共有する”という言葉でした。
これまで、報告の際に結果だけを伝えてしまい、上司との認識にズレが生じることがありました。
今後は、業務の進捗や課題もこまめに共有し、チームで解決策を検討できるよう意識します。」
感想文のポイント ―「気づき・行動変化・今後の目標」
感想文は「よかった」「ためになった」で終わらせず、気づき → 行動 → 成果というストーリー構成を意識するのがコツです。
■ 感想文の3要素
- 気づき(Insight)
研修中に感じた印象的な学びを明確に書く。
例:「自分は報告を“義務”として捉えていたが、“信頼構築の手段”だと理解した。」 - 行動変化(Action)
実際に取り入れたい行動や意識の変化を書く。
例:「小さな成果でも日報にまとめ、上司と共有する習慣をつけたい。」 - 今後の目標(Goal)
今後のキャリア・仕事にどう活かすかを示す。
例:「半年後には後輩への指導ができるよう、報連相の質を高めたい。」
■ 感想文の例文
「2年目研修では、自分の強みと弱みを客観的に見直すことができました。
チームでの役割を意識し、相手に“伝わる報告”を心がける大切さを実感しました。
今後は、上司だけでなく後輩にも丁寧に説明できるよう、日々のコミュニケーションを磨いていきたいです。」
このように、「気づき → 行動 → 目標」が明確な感想文は、評価されやすく印象に残ります。
フォローアップ研修とのつなげ方(2年目フォロー研修/フォローアップ研修)
2年目研修は、単発で終わらせず、**フォローアップ研修(半年後・1年後)**とセットで実施されるケースが多いです。
この際、レポートや感想文の内容は「前回の学びをどこまで実践できたか」を振り返る重要な資料になります。
■ つなげ方のポイント
- 研修後に立てた行動目標を、定期的に見返す(自己点検)
- 上司との面談で、実践成果と課題を共有する
- フォローアップ研修で「改善事例」や「再挑戦テーマ」を発表する
■ フォローアップ研修の主な内容
- 研修レポート発表・成功体験の共有
- 失敗・課題の振り返りワーク
- 新たな目標再設定(キャリアデザイン・メンタルリフレッシュ)
このサイクルを継続することで、学びの定着率が大幅に向上し、離職防止やモチベーション維持にも効果を発揮します。
評価される行動変容とは?(現場上司・人事から見た視点)
研修レポートやフォローアップ面談で最も評価されるのは、「学びを行動に移したか」です。
上司や人事が重視するポイントは、次の3点に集約されます。
■ ① 再現性のある成長
研修で学んだことを、日常業務で再現できているか。
例:「報連相を改善し、上司からの確認事項が減った」など、具体的成果が見えると高評価です。
■ ② 周囲への良い影響
自分の変化が、チーム全体の成果や雰囲気に波及しているか。
例:「後輩への声かけが増え、職場の連携がスムーズになった。」
■ ③ 継続性・自発性
研修後も自ら学びを継続しているか。
例:「月に一度、自分で課題を設定し、上司に報告している。」
これらの行動変容が確認できると、上司や人事から「成長意欲の高い社員」と評価され、昇進・昇格の際にもプラスになります。
2年目研修でよくある質問(FAQ)
2年目研修は、多くの企業や公的機関で行われている“節目の研修”ですが、初めて参加する人にとっては疑問や不安も多いものです。
ここでは、よくある質問をまとめて解説します。
2年目研修は必ず受けないといけない?
基本的に、企業・病院・自治体が実施する研修は「必須」扱いです。
出席が人事評価や昇進条件に含まれているケースも多く、「任意」とされていても、参加が望ましいとされています。
研修の目的は、単なる形式ではなく「自立・主体性を高める機会」として位置づけられています。
やむを得ず欠席する場合は、事前に上司や人事担当に理由を伝え、**代替課題(レポート提出や別日参加)**の指示を受けましょう。
2年目研修の服装、スーツは必須?
服装は研修の主催元によって異なりますが、原則はスーツまたはオフィスカジュアルが基本です。
「社会人としてのマナー」「受講態度の印象」を問われる場であるため、迷ったらスーツを選ぶのが無難です。
- 企業研修:黒・紺・グレーなどのスーツ着用が一般的
- 公務員・教員研修:ビジネスカジュアル可だが清潔感が重要
- 医療・看護・保育研修:ユニフォームまたは白衣での参加もあり
また、オンライン研修の場合も上半身はきちんとした服装を心がけましょう。
身だしなみは「社会人としての基本姿勢」を映す要素です。
2年目研修を休む場合の対応は?
体調不良や勤務都合で参加できない場合は、必ず事前連絡を入れることが大前提です。
多くの企業では、無断欠席は評価に影響する場合がある無断欠席は「意欲が低い」「責任感がない」と見なされる可能性があるため注意が必要です。
欠席時の対応例:
- 上司・人事・教育担当へ連絡(理由と復帰予定を明確に)
- 資料の共有依頼(講師資料・スライドなど)
- フォローアップ対応(研修録画視聴・レポート提出など)
特に医療・公務員など公的職種では、欠席理由の報告書提出が求められる場合があります。
無理に出席せず、指示に従い誠実な対応を心がけましょう。
研修医2年目の英語・何科・試験は?
医師臨床研修制度では、2年目になると専門科の選択と次のキャリア準備が始まります。
主なポイントは以下の通りです。
- 英語:論文・国際学会発表・英語診療への対応力強化が必要
- 何科を選ぶか:2年目後半に専門研修(後期研修)先を決定する流れ
- 試験:各病院・大学での選抜試験・面接・推薦書提出が中心
英語研修や海外医療プログラムを2年目に導入している病院もあり、
早期から語学力を磨くことで進路選択の幅が広がります。
教員・公務員・看護師の地域別研修スケジュールは?
教員・公務員・看護師の2年目研修は、自治体や所属機関によって時期や内容が異なります。
- 教員(千葉県・鳥取県・大阪府など)
年度中に複数回開催(授業研究・校内OJT・集合研修など)
例:千葉県では「教育実践力向上研修」、鳥取県では「地域連携型研修」など。 - 公務員
地方人事委員会や人事院支部主催で実施。組織理解・法令遵守・リーダー育成を重視。 - 看護師
日本看護協会および各医療機関の教育委員会が主催。
テーマは「リーダーシップ」「チーム連携」「新人指導」などが中心。
自治体によってはオンライン化が進み、遠隔研修やeラーニングが導入されています。
自分の勤務先・所属自治体のスケジュールを必ず確認しておきましょう。
2年目研修を「自立のきっかけ」に変える

2年目研修は、単なる“振り返り”ではなく、「社会人としての自立を形にする」大切な通過点です。
ここでは、研修をより実りあるものにするための3つの視点を紹介します。
研修を受ける目的を明確にする
まずは“なぜこの研修を受けるのか”を自分の言葉で定義しましょうまず大切なのは、「なぜこの研修を受けるのか」を自分の言葉で定義することです。
受け身の姿勢ではなく、**“自分の成長テーマを持って臨む”**ことで、研修効果は何倍にも高まります。
例:
- 「自分の仕事を任せてもらえる存在になる」
- 「チームに貢献できる行動を増やす」
- 「将来のキャリアを具体的に描く」
目的を明確にすることで、学びの取捨選択ができ、実務への応用力も上がります。
学びを現場で実践する3つのポイント
- 1つだけ行動を変える
全てを一度に変えるのではなく、「明日からできる小さな行動」を1つ決める。 - 振り返りの習慣を持つ
1週間に一度、できたこと・できなかったことを記録する。 - 他者の視点を活かす
上司・同僚・後輩にフィードバックを求めることで、客観的な成長を実感できる。
これらを繰り返すことで、**“研修で終わらせない実践型成長サイクル”**が定着します。
3年目以降へのキャリアステップにつなげる
2年目研修で得た学びは、3年目以降のキャリア形成の土台になります。
特に次の3つの方向性を意識しましょう。
- 専門性の深化:自分の得意分野を伸ばし、強みを確立する。
- 後輩指導・マネジメント:リーダーシップを意識し、人を育てる視点を持つ。
- キャリアデザイン:3年後・5年後の理想像を描き、今の行動に落とし込む。
2年目研修は、言い換えれば「プロとしての自立宣言」です。
学びを行動に変え、3年目の飛躍につなげることが、社会人としての成長を決定づけます。
2年目研修は“振り返り”ではなく“再スタート”。
自分の役割を再認識し、学びを行動に変えることで、
社会人としての軸が定まり、次のキャリアが自然と見えてきます。
資料ダウンロード
超実践型ビジネススキル研修
新入社員・若手研修一覧はこちら
新入社員向けのスキル研修やマインド研修をご用意しています。
お気軽にお問い合わせください。

大学卒業後、外資系医療機器メーカーで営業に従事。
6年間で8人の上司のマネジメントを経験し、「マネジャー次第で組織は変わる」と確信し、キャリアチェンジを決意する。
2009年にワークハピネスに参画し、チェンジ・エージェントとなる。
医療メーカーや住宅メーカーをはじめ、主に大企業の案件を得意とする。また、新人から管理職まで幅広い研修に対応。
営業、営業企画、新人コンサルタント教育を担当後、マーケティング責任者となる。
一度ワークハピネスを退職したが、2021年から復帰し、当社初の出戻り社員となる。現在は、執行役員 マーケティング本部長。