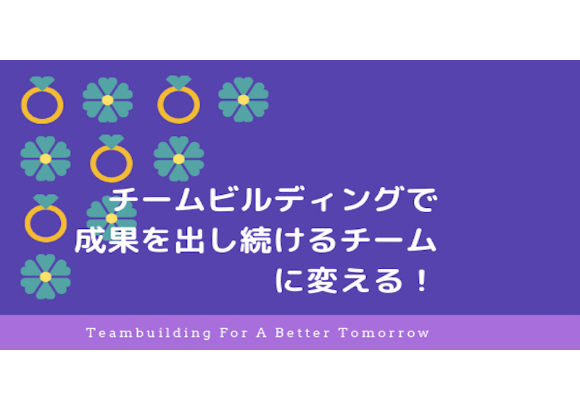チームマネジメントとは?成果を最大化するための実践手法とマネジメントの基本を紹介
働き方の多様化やリモートワークが普及し、価値観の違いが顕在化する現代においては、チームをまとめて最大限の成果を引き出す「チームマネジメント」の重要性が高まっています。
チームマネジメントでは、タスクを割り振るだけではなく、メンバーの能力や性格に応じて適切に指導・支援して、チーム全体の力を底上げすることを目指すものです。
本記事では、チームマネジメントの定義から基本スキル、成功のポイント、そして具体的な改善策まで、組織運営に役立つ情報を網羅的ご紹介します。
チームマネジメントとは?定義と基本的な考え方

チームマネジメントを効果的に実践するためには、目的や役割を正しく理解することが重要です。チームマネジメントの定義や基本的な考え方を、詳しく見ていきましょう。
チームマネジメントの意味と目的
チームマネジメントとは、複数のメンバーで構成されるチームが共通の目標を達成するための管理手法です。各メンバーの能力を最大限に活用し、組織として最高のパフォーマンスを発揮させることを目指します。そのためには一人ひとりの特性や強みを理解し、適材適所の配置や個別の成長支援を行うことが必要です。
チームマネジメントでは、メンバーの自律性を促進し、創造性や主体性を引き出すことが重視されます。管理者が一方的に指示を出すのではなく、メンバーが自ら考え、行動できる環境を整備するのです。
マネジメントとリーダーシップの違い
マネジメントは「管理」に焦点を当てた概念です。管理の対象は社員だけでなく、企業の資源・資産やリスク、業務上の計画を含めた総括的な取組となります。
一方リーダーシップは「導く」ことに重点を置き、ビジョンの提示や動機づけ、変革の推進といった人間的側面が強調されます。
なおリーダーシップには、さまざまな分類があります。特に近年は、部下との関係を大切にする「トランザクショナルリーダーシップ」や、メンバーに奉仕・支援することを重視する「サーヴァントリーダーシップ」など、相手との相互的な関係を重視する方法が主流です。
マネジメントでは、既存のシステムや手順を効率的に運用して、成果を出すことが求められます。リーダーシップのように「信頼される個人」がトップに立つのではなく、組織全体の仕組みとして、目標達成のために機能するのです。
チームビルディングとの違い
チームビルディングは、チームの結束力や協力関係を構築することに特化した活動で、主に関係性の向上を目的としています。メンバー間の信頼関係の構築やコミュニケーションの活性化などに重点が置かれたアプローチです。
一方、チームマネジメントはより包括的な概念です。チームビルディングを含めた日常的な業務管理など、継続的な活動全体を指します。
チームビルディングが「チームの土台作り」だとすれば、チームマネジメントは「チームの継続的な運営と成長」を担う役割といえるでしょう。
チームマネジメントが必要な理由
現代のビジネス環境では、適切なチームマネジメントが欠かせません。チームマネジメントの活用で、社会課題や時代的な需要への対応が期待されているからです。いまだからこそ、チームマネジメントが必要とされる理由を見ていきましょう。
成果に直結するチームを作ることが重視されている
企業では、限られた資源で最大の成果を上げることが強く求められています。個人の能力に依存した組織運営では、変化の激しい市場環境に対応することが困難だからです。さらに人材不足も深刻化するなか、チーム全体で高いパフォーマンスを発揮できる組織作りが不可欠となっています。
チームマネジメントでは、メンバーそれぞれの専門性や経験を活かした取組が行われます。一人では解決できない複雑な課題にも対応できるだけでなく、適切な役割分担と連携によって作業効率も向上するのです。
メンバーの個性やジェンダーギャップに対応したチームづくりが必要
職場の多様性が進む現代では、さまざまな背景を持つメンバーが協働する機会も増えています。年齢や性別、国籍、働き方への考え方などが異なるメンバーが、働きやすい環境を整備しなくてはなりません。
さらに育児や介護などのライフイベントへの対応では、個々の状況に応じた柔軟なマネジメントが求められます。
それぞれの状況に適した働き方や評価制度を設計することが、多様性を活かしたチーム作りの重要なポイントです。
キャリア支援による離職や人手不足への対策になる
少子高齢化を背景にした人材不足が深刻化する昨今、優秀な人材の離職防止は、企業にとって重要な課題のひとつです。適切なチームマネジメントを通じてメンバーのキャリア開発と成長支援を行うことで、組織への定着率を高めることができます。
一人ひとりの将来的なキャリア目標を把握し、現在の業務と結びつけることは、仕事に対するモチベーションにもつながります。また新しい業務への挑戦やスキルアップ支援で、メンバーが成長を実感できる環境を整備することも重要です。チームマネジメントによってこうした機会を適切に設定し、個人の希望や能力にあわせた技術開発を進めることで、人材の定着率向上と組織力強化の両方を実現することができるのです。
チームマネジメントに必要なスキルと要素
効果的なチームマネジメントを実践するためには、いくつかのポイントがあります。ここでは特に重要な5つのスキルについて、まとめました。
コミュニケーション能力
チームマネジメントの基盤となるのがコミュニケーション能力です。情報伝達だけでなく、相手の話を理解し、状況を把握することが大切です。
そのためには、異なる背景や価値観を持つメンバー間での対話が可能になるよう、仕組みを整えなくてはなりません。オープンなコミュニケーションで悩みや課題を共有し、それぞれが補助し合える環境整備が求められます。
各メンバーに合わせたコーチング・指導力
指導やコーチングでは、特性や能力、成長段階に応じて、最適な指導方法を選択する必要があります。同じ内容でも、相手によってアプローチを変えることで、組織全体の理解度をそろえるのです。
必要に応じて追加の研修等を設定したり、個人の意欲にあわせた自主学習の環境を整えたりするなど、柔軟な対応を心がけましょう。
さらに適切なタイミングでフィードバックを提供し、メンバーの自己認識と改善意欲を促進することも重要な要素となります。
プロジェクトとメンバーのスケジュール管理力
限られた時間と資源の中で最大の成果を上げるには、スケジュール管理も欠かせません。プロジェクト全体の工程管理だけでなく、各メンバーの業務負荷や個人的な事情も考慮した現実的な計画立案が求められます。タスクの優先順位や依存関係を明確にし、リスクの予測と対策を共有しましょう。
また進捗状況を定期的に確認し、必要に応じて計画を調整する柔軟性も必要です。特に予期しない問題が発生した際には、迅速な代替案への移行が求められます。メンバー同士が互いの進捗状況を把握しあうことで、業務の交代もスムーズになるのです。
目標の設定・達成力
明確な目標設定は、チームの方向性を示し、モチベーションを維持するためにも役立ちます。具体的で測定可能であり、期限が明確に設定された目標を立てましょう。
また一人ひとりが自分の目標やキャリアプランにあった目標を立てることで、組織の成長が自分の成長とつながることを実感できます。
目標達成のプロセスでは、中間マイルストーンの設定も有益です。定期的に進捗を確認し、小さな成功を目視することが、達成感と自信を育てるのです。目標達成過程で得られた学びや改善点を次の目標設定に活かすことで、チーム全体の成長サイクルを確立することにもつながります。
KPIやOKRを活用するのも有効です。KPIは、売上高や顧客満足度などの具体的で測定可能な指標を設定し、チームの進捗状況を客観的に把握します。またOKRは野心的な目標に対して3〜5つの測定可能な結果を設定するフレームワークです。
こうした指標を活用することで、個人の貢献度とチームの成果の関係性を明確化し、公正で納得感のある評価制度を構築できます。
課題解決力と意思決定能力
チームマネジメントでは個人が直面したトラブルや課題を解決し、共有することで、組織全体の持続的な改善につながります。
リスクやチャンスを適切に評価し、チーム全体にとって最良の選択を目指しましょう。
また決定した内容をメンバーに分かりやすく説明し、納得感を得ること必要です。チームメンバーの意見や提案を積極的に取り入れ、できるだけ多くの共感を得るよう努めることで、一人ひとりが自分事として課題解決に挑む姿勢が育ちます。
チームマネジメント時に発生しやすい課題と原因
チームマネジメントの過程では、多くの課題に直面します。よくある課題を事前に理解し、適切な対策を講じてことで、大きなトラブルへの発展を防ぎましょう。
チームメンバーや部下への理解不足
多くのリーダーが抱える根本的な問題のひとつが、メンバー個々の特性や状況への理解不足です。チームマネジメントでは業務スキルや経験年数だけでなく、価値観やモチベーションの方向性、キャリア目標、プライベートな状況なども含めた包括的な理解が必要です。
メンバーへの理解が不足した状態では、不適切な業務配分や指導方法によるトラブルを防げません。また、メンバーが抱える悩みや課題を放置することで、問題が深刻化する恐れもあります。
定期的なミーティングや日常的なコミュニケーションの機会を増やし、メンバーの変化に敏感に気づきやすくする仕組みを整えましょう。
現場への理解力不足
管理職になると、現場の実務から離れることが多くなります。業務の実態や現場で発生している問題を、正確に把握できていないかもしれません。
現場理解の不足は、無理なスケジュールや不適切なリソース配分などの問題を引き起こします。また、メンバーからの相談や提案に対して的確なアドバイスができず、信頼関係の悪化につながることもあります。
定期的に現場へ出向き、メンバーからの詳細な業務報告を受けるなど、実際の業務での変化に気を配りましょう。
管理職の負担が増加している
現代の管理職は、従来の管理業務に加えて、メンバーのメンタルヘルスケアや多様性への対応、働き方改革への対応など、多岐にわたる責任を負っています。さらに自身の成果も求められることが多く、管理業務との両立が困難になっているケースがあるのです。
負担増加によって管理職自身が疲弊すると、適切なマネジメントはできません。判断力が低下し、チーム全体のパフォーマンスに悪影響を与えることもあります。
業務の優先順位を明確にし、委譲できる業務は積極的にメンバーに任せるなど、自分自身のマネジメントも大切にしてください。
トラブルの再発防止するためのシステムが課題になることも
チーム運営では、類似したトラブルや問題が繰り返し起こることがあります。これは問題の根本原因が特定されていなかったり、対策が表面的だったりすることが原因です。また学習した内容が組織に定着していない場合にも、根本的な解決にはつながりません。
問題発生時の詳細な記録を分析し、根本的な原因を特定することで、具体的な改善を目指しましょう。さらに学んだ教訓をチーム全体で共有し、組織の知識として蓄積する仕組みを構築することも必要です。
チームマネジメントの改善・強化のポイント
効果的なチームマネジメントを実現するためには、戦略的なアプローチと継続的な改善が重要です。効果的なチームマネジメントのためのポイントを解説します。
1on1ミーティングを活用する
1on1の効果を最大化するためには、頻度と時間の設定が重要です。週1回など定期的に実施することで、メンバーとの関係性を深めることができます。また業務の進捗報告だけでなく、キャリアの悩みや職場環境への要望、チャレンジの希望なども含めて自由に話し合うことが大切です。
リーダーにとって1on1は、メンバーの本音や課題を把握し、個別に最適化したサポートのための時間となります。さらにメンバー側も定期的に自分の状況を振り返る機会となり、自己成長への意識が高まります。
継続的に実施することで、チーム全体のエンゲージメント向上と生産性向上が期待できる取組です。
メンバーのモチベーション維持を意識したマネジメント
メンバーのモチベーション管理は、持続的な高パフォーマンス実現のために欠かせない要素です。
モチベーション管理では、内発的動機と外発的動機の両方に配慮する必要があります。内発的動機については、仕事の意味や社会的価値を明確にし、メンバーが自分の役割にやりがいを持てるような環境を整備しましょう。
また外発的動機については、公正な評価制度の運用や適切な報酬体系の整備、キャリアアップ機会の提供などが効果的です。小さな成功や改善をきちんと認識し、感謝の気持ちを表現することで、メンバーの自己効力感を高めることができます。
また、フレームワークを活用するのもおすすめです。たとえばタックマンモデルは、チームの発達段階を5段階で捉え、各段階に応じたマネジメント手法を選択できます。
ベルビン理論ではメンバーの役割を9つのタイプに分類し、バランスの取れたチーム編成を行います。さらにPM理論は、リーダーシップを目標達成機能と集団維持機能の2軸で分析し、状況に応じた最適なスタイルを選択可能にする方法です。
メンバーやチームの状況に合わせて、適切なフレームワークを適用しましょう。
他チームリーダーからのアドバイスを反映させる
チームマネジメントのスキル向上には、他の成功しているチームリーダーからの学びも有益です。組織内外のネットワークを活用し、成功例や失敗事例を共有することで、自分だけでは気づかない改善点や新しいアプローチを発見できます。
また、経験豊富なリーダーから継続的な指導を受ける仕組みも効果的です。業界団体やセミナー、研修などの外部リソースも積極的に活用し、最新のマネジメント手法や他社の成功事例を学ぶことで、理想的なリーダー像を明確にできます。
学んだ内容は自分のチームの状況に合わせてカスタマイズし、段階的に導入してみましょう。
業務プロセスの見直しと導入を行う
チームマネジメントでは、ビジョンマネジメントや戦略マネジメント、PDCAマネジメント、メンバーマネジメントを組み合わせて運用することが効果的です。
ビジョンマネジメントはチームの目指すべき姿と価値観を明確に定義し、メンバー全員で共有するものです。日々の業務と大きな目標とのつながりが明確になり、メンバーの当事者意識と責任感が向上します。
戦略マネジメントでは、ビジョン実現のための具体的な計画と施策を策定し、限られたリソースを効果的に配分します。
PDCAマネジメントでは、計画の実行・結果の検証・改善点の特定・次期計画への反映というサイクルを確立し、継続的な改善を実現します。
さらにメンバーマネジメントでは、個々のメンバーの成長と貢献を最大化するための個別支援を提供します。
こうした要素を連携させることで、よりよいチームの構築が可能になるのです。
成功企業に学ぶチームマネジメントの実践事例

チームマネジメントでは、成功事例から学ぶことも多くあります。
ここでは実際に実施されたチームマネジメントの研修事例を通じて、効果的な手法と導入のポイントを学んでいきましょう。
事例1:若手の早期教育化を目的にしたチームマネジメント研修を実施
あるメーカーでは、若手社員の役割意識がまだ薄い状態にあり、主体的な動きが少ないことが課題でした。
与えられた業務だけでなく、自ら周囲に働きかける力を身に着けるためには、まず自身の役割と企業の成長ビジョンを理解することが必要です。自分が会社に貢献していることを自覚して、能動的なアクションを取ることを目指したのです。
そこで、若手を対象とした研修として、業務内容をシミュレーションできるゲームを実施しました。ゲームを通じて他の人を巻き込み、チームとして活動することの重要さを学びます。特に状況が変化した場面では、他チームとの情報交換が重要になりました。
こうした経験は研修後、「互いに補い合いながら仕事をする」意識に繋がりました。
事例2:リーダーシップやチームマネジメントの手法を学べる研修を実施
組織内では、コミュニケーションが縦のラインに限定されたり、他部署との情報交換がなされなかったりするケースも多く見られます。こうした気風では協力より競争が優位になり、協働の動きが弱くなりがちです。
チームにおけるリーダーには、メンバー間のコミュニケーションを円滑にし、能力を補い合って、全体の業績をあげることが求められます。
リーダーシップ研修ではチーム全体を俯瞰し、横の連携をスムーズにするための体験型実習などを行いました。研修を通じて自らの行動や考え方を振り返り、ふだんの業務へ反映させる取組です。
リーダーシップやチームマネジメントを体験として学ぶことで、自ら気づき、改善する動きが生まれるのです。
ビジョンでメンバーを引っ張る日本特殊陶業様のマネジメント研修事例はこちらでご覧いただけます。
ワークハピネスではスクエアホイールサーベイでマネジメントの課題を解決
ワークハピネスでは独自の診断ツール「スクエアホイールサーベイ」を活用し、チームマネジメントの課題を可視化する、効果的な改善策を提供しています。
従来のサーベイは、正確に問題点を特定することを目的に設計されています。問題の深堀が十分でないケースも多く、問題の根本的な解決にはつながりにくいこともあります。
ワークハピネスのスクエアホイールサーベイでは、組織の状態を1つの絵のメタファーで表すのが特徴です。問題点に対する対話を引き出すグループディスカッションを通じて、チームの現状や課題を掘り下げていくのです。
一枚のサーベイをもとにして意見を交わし、日ごろ抱えている課題を共有することで、チームが目指すべき方向性が浮き彫りになります。また継続的な研修を行うことで、組織としての仕組みづくりに結び付けていくのです。
一人ひとりの考え方や価値観を大切に、チーム全体としての一体感を持って課題解決に取り組むことで、無理なく、効果的なチームマネジメントが行えるシステムです。
チームマネジメントの社内研修が難しい場合の対策
社内でのチームマネジメント研修実施が困難な場合でも、外部リソースを活用することで効果的なスキル向上を図ることができます。
特に中小企業では、専門的な研修プログラムを内製するのが難しいケースも多くあります。外部のサービスを活用し、効果的なチームマネジメントを行うポイントをまとめました。
オンライン研修やeラーニングの導入を
オンライン研修やeラーニングは、時間と場所の制約を受けずに学習できる利便性の高い手法です。多様な働き方を導入している企業にとっても、自分のペースで学習できることは大きなメリットといえるでしょう。
オンライン研修やeラーニングでは、動画コンテンツだけでなくテストやレポート提出などで相互的なコミュニケーションが取れるサービスがおすすめです。アウトプット機会があることで、学習効果を高めることができます。
一方で、オンラインの普及によって、新たな課題が生まれています。対面での雑談や非公式なコミュニケーションが減ることで、メンバー間のコミュニケーションが減り、文字ベースのやり取りによる誤解やトラブルが発生しやすくなったのです。こうした問題は、テレワーク業務の導入時にも対応が必要な課題となっています。
オンラインで研修や業務を行う場合は、気軽な雑談や意見交換ができる場を意識的に用意しておきましょう。
社外研修やセミナーを導入するメリット
社外研修やセミナーには、業界のベストプラクティスや最新のマネジメント手法を学べることが大きなメリットです。専門的な講師から直接指導を受けることで、理論と実践の両面での深い理解を得ることができます。
また他社の参加者との交流は、異なる業界や企業規模での取り組み事例を知る機会にもなり得ます。他社間の横のつながりは、自社業務でのヒントを得られるだけでなく、将来的なビジネス関係の構築にもつながるかもしれません。
また業界によって、チームマネジメントの課題やポイントが異なります。たとえば看護・医療業界では、多職種連携やクリティカルシンキング、緊急時のリーダーシップに重点を置いた研修が効果的です。
一方介護業界では、利用者に寄り添った個別ケアの実現と、多様なスタッフの協働、身体的・精神的負担の軽減を両立させる必要があります。
さらに営業組織では、個人の成果とチーム成果のバランスを取り、競争と協力を両立させることが重要なテーマとなります。
業種にあわせた専門的なセミナーや研修を受けることで、業界内での情報交換ができるのも大きなメリットです。
オンライン研修や社外研修先の選び方
研修サービスを選択する際は、自社の課題と目標を明確にすることから始めましょう。コミュニケーション改善やリーダーシップ開発、業績管理など、重点的に取り組みたい分野を特定することが重要です。
次に、研修プログラムの内容と形式を詳しく確認します。グループワークや個別指導の有無、期間や頻度なども判断材料です。また講師の経歴や実績、過去の受講者からの評価なども参考にしてください。
また研修後のフォローアップサービスや、継続学習の仕組みがあるかも確認しておきましょう。
チームマネジメントで部下・上司ともに積極性の強化を
効果的なチームマネジメントは、管理職だけの責任ではありません。部下と上司の双方が積極的に関わることで、より強固で生産性の高いチームを構築することができます。
管理職は部下の積極性を引き出すために、安心して意見を言える環境を整えましょう。また部下の成長に合わせて徐々に権限を委譲し、自律的な判断と行動を促すことも効果的です。
一方、部下側も受身の姿勢ではなく、チームの目標達成に向けて積極的に貢献する意識を持つことが重要です。自分の役割を理解し、期待を上回る成果を目指すとともに、同僚との協力やサポートにも積極的に取り組むことで、チーム全体のパフォーマンス向上に貢献できます。
チームマネジメントの効果的な運用を目指すなら、ワークハピネスにご相談ください。チームの課題を明確に視覚化し、継続的なサポートで、よりよい環境の整備をお手伝いいたします。
チームマネジメントの成功は、メンバー全員の積極的な参加と協力によって実現されるのです。
チーム力を高める研修・ワークショップ

大学卒業後、上場派遣会社に入社し、その後、教育系子会社のエスプール総合研究所(現:ワークハピネス)へ。
各種サーベイなどの設計・開発、人事制度構築、理念浸透などのコンサルティングを経て、教育周りの企画提案を主な業務とする法人営業を担当。関西地域で大手上場企業の新規開拓をメインに携わり、お客様の理念体系、今後の戦略に沿った、「人の育成」「仕組みの整備」を体系的に提案することを得意としている。
2019年からマーケティングチームの立ち上げに責任者として関与。デジタルの力を活用して、会社の売れる仕組みづくりを構築している。