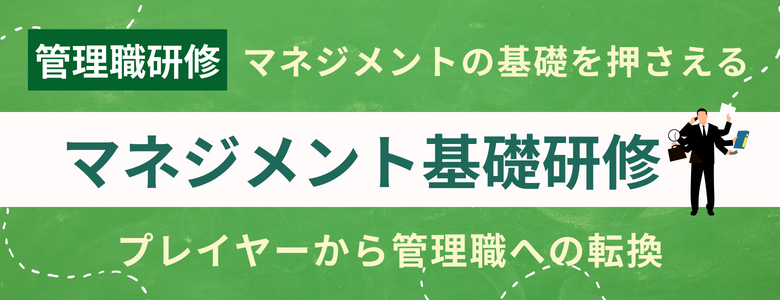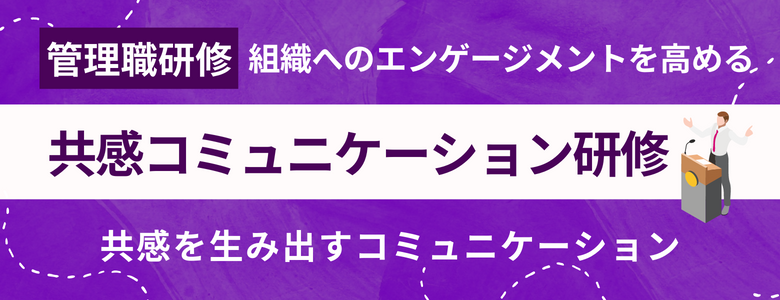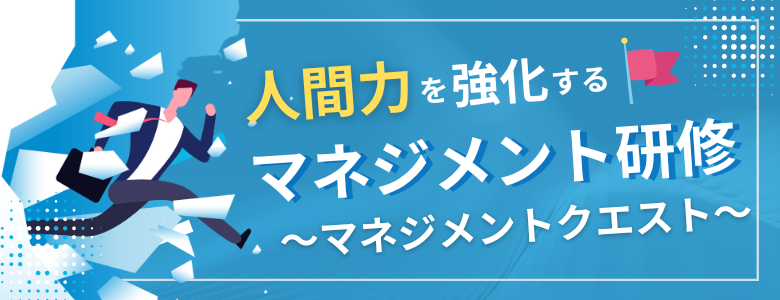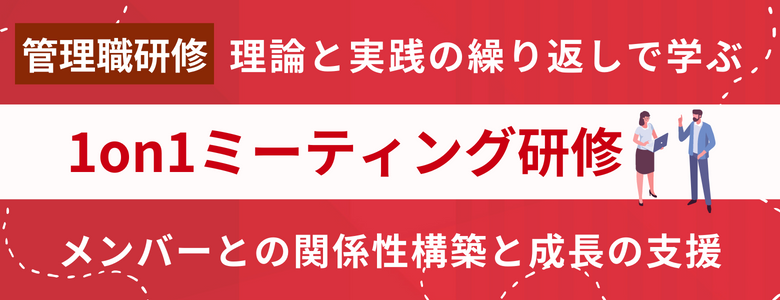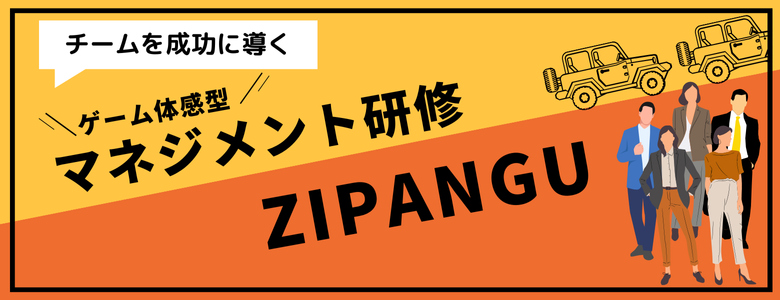管理職研修のテーマの選び方は? おすすめのテーマ13選&導入事例を紹介
組織のリーダーとなる管理職をどのように育てていくかは、現在、多くの企業が抱えている課題です。管理職の育成は、部下のパフォーマンスだけでなく、将来的な組織の成長にも大きく影響します。管理職研修は、管理職を成長させる有力な手段ですが、どのような内容の研修を受けさせるべきか悩んでいる企業も多いのではないでしょうか。
今回の記事では、管理職研修のテーマの選び方やおすすめの研修テーマ13選、管理職研修を導入する際のポイントなどを解説します。管理職研修の導入を検討されている方や研修のテーマ選びにお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
管理職研修の重要性が高まっている背景
近年、管理職研修の需要が高まっています。以下が需要が高まった理由です。
- 多様性の拡大
- VUCA時代の到来
- デジタル化の加速
それぞれの背景について、詳しくみていきましょう。
多様性の拡大
管理職研修が注目される背景の一つが、社会における多様性の拡大です。多様性が進むにつれて、職場でも異なる価値観や考え方、働き方を持つ人材の存在が当たり前になってきました。多様性のある職場は、異なる視点・アイデアをもたらし、イノベーション創出や市場変化への対応に役立ちますが、組織の管理は難しくなってしまいます。
管理職は多様な人材の所属するチームをまとめ、高いパフォーマンスを発揮するために、これまで以上にリードやサポートを行っていかなければなりません。企業が多様性を受け入れるためには、研修によって管理職に高いマネジメントスキルを身に付けてもらう必要があります。
VUCA時代の到来
VUCA時代の到来も、管理職研修の需要が高まっている背景の一つです。VUCAとは、「Volatility(変動性)」「Uncertainty(不確実性)」「Complexity(複雑性)」「Ambiguity(曖昧性)」の頭文字から生まれた造語で、将来の不確実性や予測困難な状態などを表しています。
現代社会はVUCA時代といわれ、物事の不確実性が高まり、将来予測が困難であるため、個人での成果発揮が難しくなっているのが特徴です。企業が成長を続けるためには、個人の能力のみに頼るのではなく、組織力向上やリスクマネジメントの必要性が高まっています。同時に、チームが高いパフォーマンスを発揮できるようチームをまとめる管理職のスキル向上も求められているのです。
デジタル化の加速
管理職研修が重視されている背景の一つとして挙げられるのが、デジタル化の加速です。デジタル技術の急速な発展により、管理職に求められる役割・能力も変化しました。現代では、デジタルツールの効果的な利用による業務の効率化やデータに基づく戦略・意思決定は、チームマネジメントに不可欠です。
管理職には、ツールの使用方法やデータ分析能力に加え、デジタルコミュニケーションやセキュリティに関する知識も必要とされます。しかし、全ての管理職が自らの力でデジタル化に対応できるとは限りません。今の時代に求められる能力を身に付けるため、管理職向けの研修が必要になるのです。
【3ステップ】管理職研修のテーマの選び方
管理職向け研修には多くの種類があり、実施の目的や企業が抱えている課題によって、優先すべき研修も異なります。管理職研修のテーマを選ぶ際の3ステップは以下の通りです。
- ステップ1:実施の目的を明確にする
- ステップ2:管理職がなるべき姿を明確にする
- ステップ3:管理職に不足する能力を明確にする
管理職研修のテーマの選び方を順を追って確認しましょう。
実施の目的を明確にする
ステップ1として、管理職研修実施の目的を明確にします。研修を実施する上では、「何のために行うか」がテーマ選びの大きなポイントです。同じ管理職研修でも、新任の管理職にマネジメントの基本を教育するのと、経験者がさらなるスキルアップを目指すのでは、求められる研修内容が異なります。
自社にとって適切なテーマを選択するためにも、自社を取り巻く環境や課題などの現状を正しく認識しておくのが重要です。研修を企画する前には、市場や競合他社、自社の状況を分析して戦略を立てましょう。また研修を受ける管理職が明確に目的意識を持って臨めるよう、関係者には事前になぜ研修を実施するのか、目的や目標を共有しておくのも大切です。
管理職がなるべき姿を明確にする
ステップ2では、自社にとっての管理職がなるべき姿として、該当ポジションの管理職に求められる人材要件を明確にしましょう。管理職になる人材が備えるべきスキルや知識、価値観、マインドなどをはっきりと決めておけば、目標を実現するためのプログラム選択が可能になります。
例えば、「戦略を実行するため、チームをリードしながら、部下のフォローも行える管理職」が求められる姿なら、戦略の計画立案能力に加え、組織を引っ張っていけるリーダーシップや部下のサポート力、コミュニケーション能力などが必要です。
人材要件を定義する際は、管理職に必要とされるマインド、知識・スキル、行動の3つの枠組みに分けて考えます。初めにマインドを決定し、次に持っておくべき知識・スキル、取るべき行動の順に明確化していきましょう。
管理職に不足する能力を明確にする
最後に、これまで明らかになった実施の目的・人事要件と照らし合わせ、自社の管理職に不足している能力を明確にします。必要と思われるスキルや知識から研修内容を選ぼうとすると、候補が多くなり過ぎるため、優先的に身に付けるべき能力を決めるのが大切です。
不足している能力が分かったら、「なぜ自社では求められる能力が身に付いていないのか」までを検討しましょう。能力不足が改善されない背景には、何かしらの原因が存在します。身に付かなかった原因が組織の問題であれば、組織風土や文化、組織構成から改善を試みる必要があります。一方で、個人の問題なら、根本的な原因から改善が期待できるテーマの研修を受けると良いでしょう。
管理職研修のテーマ13選

企業が実際に管理職研修を実施する場合におすすめのテーマを解説します。管理職研修におすすめの主なテーマは、以下の通りです。
- 部下の貢献意欲を上げる「ビジョニング力」
- 指導力を上げる「コーチング力」
- 部下の信頼を獲得する「共感力」
- 1on1の効果を高める「傾聴力」
- 課題を認識する「気付き力」
- 外部環境の変化に適応する「問題解決能力」
- 部下の尊敬を勝ち取る「人間力」
- 部下を納得感のある評価をする「人事考課スキル」
- 部下のやりがいを高める「MBO-S」
- チームでの成果を最大化する「チームエンゲージメント」
- 他部署・他チームとの連携を改善する「セクショナリズムの排除」
- リスクを適切に管理する「コンプライアンス」
- ”自分は大丈夫”を防ぐ「ハラスメント対策」
それぞれのテーマと身に付く能力について、詳しく解説します。
部下の貢献意欲を上げる「ビジョニング力」
ビジョニング力とは、組織のミッション(指名)・ビジョン(目指す姿)・バリュー(価値観)を現場に落とし込み、チームと一緒に実現する能力です。ビジョニング力では、チームの目指す姿を描くだけでなく、部下の自発的な行動を引き出す能力が求められます。管理職による組織のミッション・ビジョン・バリューの明確化は、社員のエンゲージメント(会社への愛着・愛社精神)を生む将来像としても大切です。
先を見通せない不確実なVUCA時代には、将来のビジョンを見据えた仕事のできる管理職の存在が欠かせません。仕事はきちんとこなすけれど、現状維持の社員ばかりで将来的な発展が見込めない場合には、ビジョニング力の研修を取り入れるのがおすすめです。
指導力を上げる「コーチング力」
コーチング力とは、本人が持つ能力や可能性を引き出し、主体的な行動によって目標達成や自己実現を促す能力です。コーチングでは、部下に直接答えを教えるのではなく、部下が自力で答えを出すためのサポートを行うことに重きを置きます。
コーチングと比較されることが多いティーチングですが、両社は似て非なる指導方法です。ティーチングとは、先生が生徒に教えるように経験者が他者に知識・スキルを伝える指導方法なので、自力での解決をサポートするコーチングとは異なります。
コーチングとティーチングはいずれも効果的な手法で、部下への指導では使い分けが大切です。コーチングの重要性を知っていても、ティーチングとの使い分けまでは実現できていない管理職も多く、研修が必要な能力といえるでしょう。
コーチング力やコーチングの研修について、さらに詳しく知りたい方は、こちらのページも併せてご覧ください。
部下の信頼を獲得する「共感力」
共感力とは、他者の意見や感情に寄り添う力で、部下と対話する上で重要になります。今の時代に部下から求められているのは、頭ごなしに厳しい意見を突きつけてくる上司ではなく、部下の意見に耳を傾け、共感を示しながら仕事を進めてくれる上司です。単に仕事をこなすだけだったり、一方的に命令を出したりする上司だと、部下から信頼を得るのは困難でしょう。
部下の不安や意見を理解するとともに、適切なサポートや意見交換を行うためには、部下に寄り添う共感力が求められます。共感力を高めて部下から信頼される上司になれば、部下のエンゲージメントやモチベーションの向上にもつながるでしょう。相手にうまく共感を示すスキルを自力で身に付けるのは難しい場合もあるため、管理職研修が効果的です。
共感力を向上させるための研修については、こちらのページも併せてご覧ください。
メンバーの共感を生み出すコミュニケーション研修「ストーリーテリング」
1on1の効果を高める「傾聴力」
傾聴力は、相手の話に耳を傾け、よく聴き理解する能力です。傾聴力は、部下との関係性を高め、信頼を築くために重要です。部下との面談や1on1ミーティングがうまくいっていない、思ったような効果が上がっていないと感じる場合、傾聴力不足が疑われます。
部下との1対1での対話では、単に「耳」で相手の話を聞くだけでは不十分です。「目」を使って部下をはっきりと見るとともに、「心」から相手に関心を向けて、はっきりと話を「聴く」必要があります。
また傾聴では、相手に対するリスペクトも大切です。結論ありきではなく、部下の意見や気持ちを最後まできちんと聴いて理解する共感・受容能力が求められます。上司と部下のように上下関係があると、なかなか傾聴力が発揮されない場合もあるため、うまく研修を活用しましょう。
傾聴力を向上させるための研修については、こちらの記事も併せてご覧ください。
課題を認識する「気付き力」
気付き力とは、今まで気付かなかった問題点に気付く能力です。仕事や部下の育成では、小さな気付きが大切になる場面があります。特に自分の課題を認識できないでいると、できていないのにできていると勘違いしてしまって、マネジメント全体に悪影響を及ぼす恐れがあるため注意が必要です。管理職は固定観念や思い込みを捨てて広い視野を持つ必要があり、物事に気付く力が求められます。
気付き力が低いと視野が狭くなってしまい、チームや自分自身の課題に気付けません。管理職は、上司としてだけでなく、部下や経営者など、さまざまな立場の視点を取り入れる力を磨いていきましょう。
気付き力向上につながるマネジメント研修については、こちらのページも併せてご覧ください。
管理職向けゲーム体感型マネジメント研修「ZIPANGU(ジパング)」
外部環境の変化に適応する「問題解決能力」
問題解決能力は、管理職にとって、部下やチームの課題を解決してパフォーマンスを高めるため、なくてはならないスキルです。問題解決能力を身に付けるためには、問題発見→目標設定→原因究明→解決策の選択→実行という一連のプロセスを一通り管理職自身でこなせるようにならなくてはなりません。
問題解決能力には、職場の課題点や原因などを見つけ出す思考力や予想外の出来事にも対処できる柔軟な対応力、解決に向けた道筋を論理的に考え出す分析・判断力など、幅広い能力が求められます。反対に、問題解決能力が低い管理職だと、イレギュラーな事象に対応できません。VUCA時代の現代においては、外部環境の変化に適応できないと、個人とチームの生産性や業務効率に大きく影響する恐れがあります。
部下の尊敬を勝ち取る「人間力」
人間力とは、人として自立し、社会に適応するために必要となる基礎的かつ総合的な能力です。多様化が広がり、急速に変化する社会では、管理職自身が持つ人間力が重視される傾向があります。上司には、職務能力だけでなく、人間的な魅力も備わっていなければ、部下の共感や心からの尊敬は得られないでしょう。
人間力は、学問や学びを活用する力(知的能力)・対人関係力・自分を律して自分らしく生きる力(自己制御力)など、幅広い能力に分類できます。人間力を持ったリーダーになるには、多様な学びが必要です。しかし、現代のマネジャーは多忙で学習のためにまとまった時間を取るのが難しいため、研修などを利用して人間力を高めていくことが大切です。
人間力を育成するためのマネジメント研修については、こちらの記事も併せてご覧ください。
部下を納得感のある評価をする「人事考課スキル」
管理職には、企業が定めた基準に基づいて人事評価を行うための、適切な人事考課スキルも必要です。部下の人事評価を実施する場合には、人事考課面談が重要となります。管理職は、部下を評価するための面談で、適切に部下の能力を把握できなければなりません。
公正公平かつ部下の信頼やモチベーションを損なわない人事考課にはスキルが必要です。部下との面談内容を基に、普段の仕事の成果と併せて人事考課や今後の目標を適切に導き出さなければなりません。
また上司・人事担当者は、部下に対する好き嫌いなど、心理バイアスの影響にも注意が必要です。研修では、管理職に必要とされる、部下を正しく評価するためのポイントを学びます。
管理職向けの人事考課研修については、こちらの記事も併せてご確認ください。
部下のやりがいを高める「MBO-S」
MBO-S(Management by Objectives and Self-Control)とは、ピーター・ドラッカーが提唱した目標管理制度です。社員が自ら目標を設定して能動的に取り組むことで、モチベーションの向上や成果につなげます。
単に上から与えられる目標をこなすのではなく、社員のセルフコントロールが含まれる点が通常の目標管理と異なります。一般的にノルマ達成は目標になってしまいがちなので、チームのメンバーが自分から達成を目指せる環境作りが重要です。研修を通じて、実際に職場でMBO-Sを取り入れるための方法を学びましょう。
チームでの成果を最大化する「チームエンゲージメント」
チームエンゲージメントとは、組織やチームに貢献したいと考える自発的な意欲やチームとの結び付きを表す用語です。複雑化していく現代社会では、組織は個人ではなくチームでの成果を前提に設計されるようになっています。管理職にも、チームを良い状態に保ちメンバーそれぞれが能力を発揮して、相乗効果によりチーム全体のパフォーマンスを向上させる能力が必要です。
しかし、日本の企業は他国と比較して従業員エンゲージメント(愛着・愛社精神)が低い傾向にあります。エンゲージメントが下がってしまう理由の一つに上げられるのが、上司との関係です。チーム力強化研修で、部下と良好な関係を築きながらチームエンゲージメントを向上させるスキルを身に付けましょう。
チームエンゲージメントを高めるチーム力強化研修については、こちらのページも併せてご覧ください。
他部署・他チームとの連携を改善する「セクショナリズムの排除」
セクショナリズム(sectionalism:割拠主義)とは、社内で自部署の利益を優先して、他部署には協力しなくなっている状態です。セクショナリズムを放置しておくと、他部署の業務妨害や自社の成長を妨げる要因になる恐れがあります。
しかし、セクショナリズムは発生しても内部からだと気付きにくいのが問題です。部署同士が排他的・非協力的になって、保身や派閥争いばかりを考えるようになると、トラブルが起こっても、原因をセクショナリズム以外のせいにしてしまう場合があります。セクショナリズムを排除するには、自社で部署間の問題が起きていないかを把握して改善する能力が必要です。
セクショナリズムの排除に役立つ管理職研修については、こちらのページも併せてご覧ください。
セクショナリズム打破!体感型ビジネスゲーム研修「ZIPANGU(ジパング)」
リスクを適切に管理する「コンプライアンス」
昨今では、SNSなどを通じて情報漏えいや不祥事が拡散しやすくなったため、企業でのコンプライアンス(法令遵守)がますます重要になりました。管理職自身がコンプライアンスを犯さないのはもちろん、チームメンバーの違反予防も管理職自身の大切な役割になっています。コンプライアンス違反が発覚すれば、企業の社会的信用の失墜や経済的損失にもつながりかねません。
管理職は、部下一人ひとりにコンプライアンス違反を防止するための教育を徹底するとともに、違反が起きてしまった場合の対処法に関しても知っておく必要があります。コンプライアンス意識を高め、実際の事例や対処法を知るためには、管理職向けのコンプライアンス研修の受講がおすすめです。
”自分は大丈夫”を防ぐ「ハラスメント対策」
近年の管理職研修では、社内でのハラスメント対策も重要になっています。どのような職場でも、意図せずパラハラ・セクハラ・モラハラ・マタハラなどが起こるものです。「うちの部署では大丈夫」「自分はハラスメントをしない」などの思い込みこそ危険と考えましょう。放っておくとハラスメント予備軍になりかねません。
しかし「自分は大丈夫」と考えている人は意外に多く、社内でハラスメント対策教育を行うだけでは不十分な可能性があります。万が一の事態が起こらないよう、管理職の価値観や指導を見直す機会が必要です。ハラスメント対策には、自分を客観視したり、周囲との認識の違いに気付いたりできる、管理職向けの集合研修を受講するのが良いでしょう。
管理職研修を導入するときのポイント

新たに研修を導入するときには、以下のようなポイントに注意しましょう。
- 個々の課題に合わせた研修を行う
- ロールプレイングを取り入れる
- 管理職の実務に慣れてから研修を実施する
- 受講者からフィードバックをもらう
それぞれのポイントを詳しく紹介します。
個々の課題に合わせた研修を行う
管理職研修を実施する際は、一人ひとりの職務や必要なスキルに応じて個々の課題に合った内容を選択しましょう。全体向けの研修だけでは、個人の課題までサポートしきれない可能性があります。管理職全員が受ける研修とは別に、個々に不足する能力や希望するキャリアに合った研修を取り入れるのが重要です。テーマだけでなく、研修期間や研修の効果なども考慮に入れて、管理力がステップアップにつながる研修体制を整えていきましょう。
ロールプレイングを取り入れる
管理職研修では、座学だけでなく実際の現場で活用するための工夫を取り入れることが大切です。座学ばかりだと受け身になってしまい、なかなか知識やスキルを自分のものにできません。インプットした内容を研修の中でアウトプットできれば、学習した内容が自然と身に付くようになるでしょう。特にロールプレイングがある研修を選ぶと、現場でも実践しやすく、研修効果の向上が期待できます。
管理職の実務に慣れてから研修を実施する
管理職研修は、実施のタイミングもポイントです。基本的には、対象者が管理職の実務に慣れてから研修を行いましょう。配属されたばかりの頃は、管理職としての業務に慣れるのに忙しく、研修内容まで身に付ける余裕がありません。一定程度実務に慣れていないと、研修を行っても新たなスキルや知識をインプットするのは難しいでしょう。目安としては、管理職に着任してから3カ月程度の期間を置いて、管理職研修を実施するのがおすすめです。
受講者からフィードバックをもらう
管理職研修の実施後は、受講者からのフィードバックや感想を考慮して研修内容の改善を続けていきましょう。管理職研修を効果的にするためには、常に改善が必要です。実施して終わりではなく、参加者の声を取り入れてPDCAサイクルを回していきます。研修の内容はもちろん、日程や期間、指導方法は適切だったかなども確認すべきポイントです。実施してみないと分からない課題もあるため、フィードバックを基に、さらに効果を向上させていきましょう。
管理職研修の導入事例
ワークハピネスで実施している以下の管理職向け研修プログラムから、実際の研修事例を紹介します。
- 管理職から行動を起こす人間力強化研修
- 課題発見力を向上させるマネジメント研修
それぞれの研修について詳しくみていきましょう。
管理職から行動を起こす人間力強化研修
まずはインターネットを利用してソフトウェア開発を行っている、株式会社クローバー・ネットワーク・コム様で実施した管理職マネジメント研修の事例です。若手社員と管理職の間でのコミュニケーション不和や管理職のチャレンジ精神不足など課題解決のため、人間力を高めるマネジメント研修「マネジメントクエスト」を実施しました。
マネジメントクエストは、ゲーム形式でグループによる対話や講師によるコーチングを学べる研修です。管理職のコミュニケーション能力向上や上司と部下がコミュニケーションしやすい環境作りなどを目指します。研修中に出てくる試練は真剣に向き合わないと合格できないようになっているため、多くの社員が懸命に取り組みました。
結果として、「部下とのコミュニケーションが丁寧になった」「仕事を前向きに捉えるようになった」といった評価が上がっています。
課題発見力を向上させるマネジメント研修
続いては、ソフトウェアの設計・開発を手掛ける株式会社ディ・アイ・システム様で実施された課長向けマネジメント研修の事例です。同社ではさらなる成長のため、次世代リーダーとなる課長層育成の必要性が課題となっており、課長から部長代理へと成長させるために研修実施を決めました。
研修は全てオンラインで、手上げ式の複数開催で実施。受講者は課長になって期間も短く、不慣れな部分もあり、研修では、グループワークやコーチング理論学習など、多くの気付きや学びを得られたといいます。
結果、成人発達理論やコミュニケーション理論などを活かした部下とのコミュニケーション向上や、システム思考による課題発見力の向上を実現。受講者が研修に前向きで、活発に意見交換していたことを評価する声もありました。
まとめ
現代社会は、多様性や不確実性、デジタル技術の発展などにより、管理職に求められる能力も従来とは異なっています。管理職が一人ひとりの役割に応じた知識・スキルなどを身に付けるには、適切な管理職研修を実施することが重要です。管理職研修には、コーチング力や共感力など、さまざまなテーマがあるため、自社に合った研修内容を選択しましょう。
ワークハピネスが実施している「ZIPANGU(ジパング)」は、管理職向けのゲーム体感型マネジメント研修です。世界30カ国以上で導入されている組織開発専門の研修で、ゲーム形式の体験を通じて、楽しみながら管理職に必要な「気付き」を得られます。マネジメント方法や部下との接し方、部署間の連携などに悩む管理職におすすめします。自社の管理職向けに研修を考えておられる方は、ぜひ検討してみてください。
「ZIPANGU」の詳しい内容やお問い合わせに関しては、こちらをご覧ください。

株式会社ワークハピネスは人材育成研修・組織開発コンサルティングを通して
人と企業の「変わりたい」を支援し、変化に強い企業文化をつくる支援をしています。
新入社員〜管理職・役員研修のほか、全社向けチームビルディングまで
貴社の職場課題に合わせたカスタマイズ対応が可能です。
ウェブサイトにはこれまでに弊社が支援させていただいた研修および
組織コンサルティングの事例を掲載しております。ぜひご参考ください。
研修資料ダウンロード
プレイングマネージャーに最適な管理職研修

大学卒業後、外資系医療機器メーカーで営業に従事。
6年間で8人の上司のマネジメントを経験し、「マネジャー次第で組織は変わる」と確信し、キャリアチェンジを決意する。
2009年にワークハピネスに参画し、チェンジ・エージェントとなる。
医療メーカーや住宅メーカーをはじめ、主に大企業の案件を得意とする。また、新人から管理職まで幅広い研修に対応。
営業、営業企画、新人コンサルタント教育を担当後、マーケティング責任者となる。
一度ワークハピネスを退職したが、2021年から復帰し、当社初の出戻り社員となる。現在は、執行役員 マーケティング本部長。