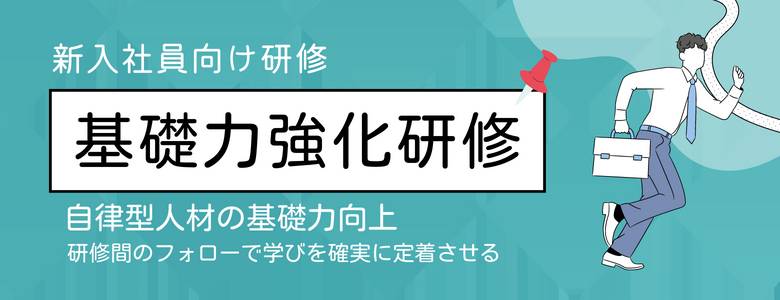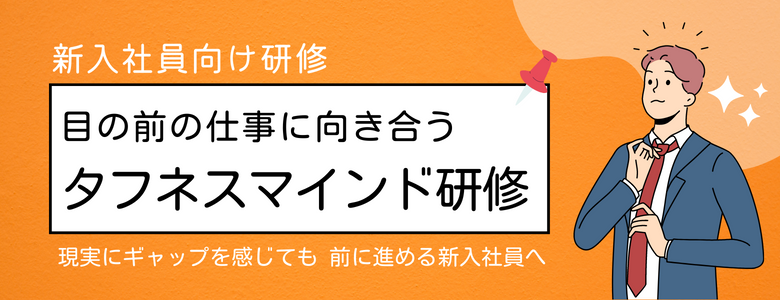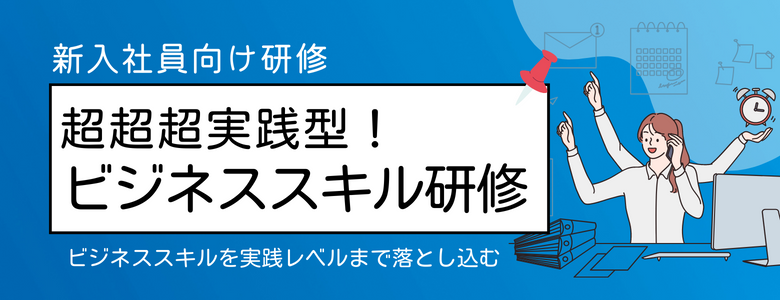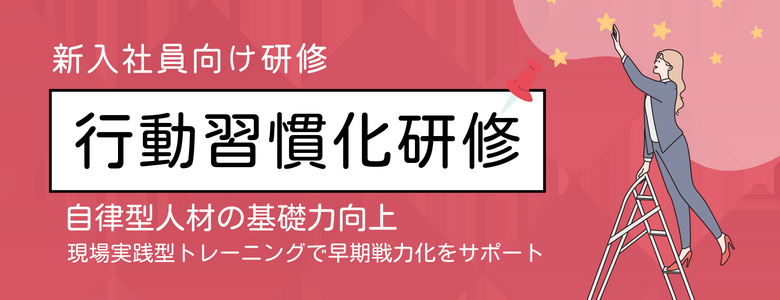近年、新入社員の行動や姿勢を「受け身がちである」と捉える企業が増えています。ほとんどの企業で取り入れられている新入社員研修は、社会人としての基礎的なスキルを身に付ける場として重要です。しかし、研修後は業務効率や成果を上げるために、新入社員の積極的な姿勢が求められます。
にもかかわらず令和の時代の新入社員は「言われたことはやるが、それ以上はやらない」「報連相などのコミュニケーションが稀薄」などの特徴があり、対応や教育方法に頭を抱える上司や教育担当者も多いです。
今回の記事では、受け身な新入社員への対処法に焦点を当て、人事担当者や研修担当者に向けて主体性の引き出し方を解説します。
受け身な新入社員の特徴
受け身の社員にはどのような特徴があるのか、いくつか挙げていきます。
- 指示されたことしかしない
上司や先輩など、誰かからの指示がないと行動に移せません。基本的には待ちの姿勢であるため、主体的に仕事をする従業員と比べて業務量や範囲が狭まります。
- 促されるまで発信しない
会議での発言や発信をしない傾向があります。「自分の発言に自信がない」「タイミングが分からない」という不安が影響していると考えられます。
- 挑戦を恐れる
受け身の新入社員は、挑戦を過度に恐れています。「失敗をしたらどうしよう」という思考から、挑戦をせず受け身の姿勢となるのです。
- キャリアアップや出世を希望しない
キャリアアップや出世を希望しないことも受け身の新入社員の特徴の一つです。「責任を背負いたくない」「安定した給料がもらえればいい」「プライベートを優先したい」という希望がキャリアアップや出世よりも優先される傾向があります。
なぜ新入社員は受け身になりがちなのか
それでは、新入社員はなぜ受け身になってしまうのでしょうか。
- 自発的な行動が苦手
- 同世代以外との接し方が分からない
- 職場環境や働き方の変化で相談しにくい環境にある
リクルートの2021年 新入社員意識調査をもとに、上記のような近年の新入社員の特徴をみていきましょう。
参考:「リクルートマネジメントソリューションズ 【調査発表】2021年 新入社員意識調査」.(2023-10-31)
若い世代は自発的な行動が苦手
リクルートの調査によると、若い世代の新入社員は自発的な行動を苦手としています。若い世代は「協働」「相手基準(相手の期待に応える)」ことを得意としており、職場環境でも「個性の尊重」と「お互いに助け合う」ことを求めています。
逆に「活気がある」「お互いに鍛えあう」などの職場環境は、10年前と比較すると求められなくなっています。「自発」「思考」などに苦手意識があることからも、若い世代は自発的に行動することに抵抗感があることが分かります。
本来、協調性があるのはプラスの要素になります。しかし若い世代は、良好な人間関係を重視するあまり、相手の意見や行動に合わせがちです。その結果、「自ら発言ができない」「指示がないと動けない」という受け身の姿勢につながるのです。
関連記事:新入社員の傾向は?Z世代を取り巻く環境や育て方を解説
同世代以外との接し方が分からない
2020年以降のコロナ禍で社会に出た若い新入社員は、同世代以外との接し方に戸惑いを感じているようです。オンラインコミュニケーションが主流である彼らは、同世代同士でもリアルな関係構築にあまり慣れていません。事実、新型コロナウイルス感染症による影響について調査したところ、64.2%もの人が交友関係やコミュニケーション不足等によるメンタルヘルス悪化に対する不安を挙げていました。(※)
またリモートワークの普及により、上司や先輩との距離感の取り方にも不安を感じがちです。デジタルネイティブな世代なのでオンラインコミュニケーションが得意ですが、対面での深い関係構築には苦手意識があります。加えて協調性が高いため、相手の領域に踏み込んで深い人間関係を築くことに対して消極的な傾向も見られます。
周囲との人間関係構築に不安を抱えていたり、消極的であったりすることで、結果的に自発的な行動に至らないことが多くなるといえるでしょう。
※参考:PR TIMES.「【コロナ禍が大学生に与えた影響とは?】3割以上の大学生が現在の授業に不満と回答!大学側が取り組むべき課題が明らかに」,(2023-10-31)
職場環境や働き方の変化で相談しにくい環境にある
職場環境や働き方の変化から、業務を行う上で分からないことがあっても、以前より周囲に相談しにくい環境になっていることも関係しています。
IT化が進んだことで、上司や先輩の作業は画面の中で行われており、手を動かしているところを「見て覚える」ことが難しくなりました。リモートワークを導入している企業であれば尚更です。
また、どのような作業をしているのか分からないことから、「今声をかけていいのか」「邪魔ではないか」という不安も生みます。リモートワークが増加したことでコミュニケーションが減っている企業が多く、相手への配慮からさらに遠慮が生じます。加えて、人材不足や同年代の先輩不足もあり、積極的な相談が難しい状況が新入社員の受け身な姿勢につながっているといえるでしょう。
新入社員の受け身な姿勢を「甘え」と切り捨てるリスク
やる気や熱意を重視してきた世代にとって、新入社員の受け身な姿勢は「甘え」と映るかもしれません。しかし、単純に「甘え」と切り捨てることには重大なリスクが伴います。
先述のリクルート調査によると、若者が仕事で重視するトップ3が「貢献」「成長」「やりがい」でした。つまり、受け身の姿勢は、やる気の不足を意味するものではないのです。むしろ、仕事へのモチベーションが高い新入社員が多いことが分かります。
一方で上司に対しては、「傾聴」や「丁寧な指導」を望んでおり、「競争」や「金銭」への希望は薄れつつあります。そのため、成長の機会が提供されない職場からは若者が離れる傾向にあります。
このような今の若者の希望や考え方を理解せず「甘え」と決めつけると、人材の定着率が低下し、採用活動にも悪影響を及ぼすリスクがあります。適切な指導を受け、環境が整えられれば、将来的な活躍は十分に期待できます。人材不足が進行する中、若者のポテンシャルを見誤ることは企業にとって大きな損失となるでしょう。
※参考:「リクルートマネジメントソリューションズ 【調査発表】2021年 新入社員意識調査」.(2023‐10‐31)
新入社員のやる気を損なう上司のNGな指導

新入社員の成長において、イマドキの若者の考え方や価値観をふまえた、適切な指導が不可欠です。新入社員の育成には上司自身の教育スキルの向上が求められます。
以下で、部下がやる気を損なうNGなアプローチを解説します。
圧力をかける
上司が部下に対して圧力をかけて指示や命令をするのは、新入社員の主体性を奪う典型的なNG指導です。
一方的な指示や高圧的な態度で接すると、部下は自身の意見を言い出しづらくなります。この状態が続くと、部下は自分で考えずに「上司の言うことを聞くだけにしよう」という思考になり、能動的に行動をしようとしません。つまり、上司が受け身な部下を作ってしまうのです。
特に若い新入社員とのコミュニケーションにおいては、相手の意見を尊重し、積極的に発言できる環境を整えることが極めて重要といえます。
業務を固定化する
業務をがっちりと固定化してしまうことも、新入社員の主体性を奪うNGな指導です。同じ作業を繰り返すことで、新しいアイデアや判断力を発揮する機会が減少し、単なるルーティンワークになってしまいます。
業務の単調化を防ぐには、部下の成長を見極めて新しい業務への挑戦をさせたり既存業務の改善をさせたりする必要があります。定期的なフィードバックやスキル向上のサポートを通じて、彼らが自ら考えて成長できる環境を整えましょう。
最低限の権限や裁量を与えない
業務権限や裁量権を与えないのも、新入社員の主体性を奪う指導に含まれます。新入社員が能力を発揮できる段階で権限を与えないと、依存体質が生まれて自己主張や発信が難しくなります。同時に業務範囲が制約されることで、新たな視点や挑戦の機会も失われてしまいます。
ある程度基礎が身に付いたタイミングで、業務権限や裁量権を与えることで、組織内の生産性向上に繋がります。新入社員の成長に合わせてどのような業務権限や裁量権を提供できるか洗い出してみましょう。
受け身な新入社員の主体性を引き出す方法

受け身ながらも成長を望む新入社員は多いことがわかりました。それでは、受け身な新入社員の主体性を引き出すには、どうすればよいのでしょうか。
最後は、受け身な新入社員の主体性をうまく引き出す方法を解説します。
新入社員の話を聞く機会を作る
新入社員の主体性を引き出すためには、新入社員の話を聞く機会を作りましょう。協調性を重視する若い新入社員は、対話を通じて主体性を発揮したいという思考があります。上司には、新入社員とコミュニケーションを取る機会を積極的に作り、新入社員の仕事に対する意欲を高めていくことが求められます。
しかし、人事担当者や教育担当者の多くは、コロナ禍以前に社会経験を積んできたため、若い新入社員とは異なる価値観や考え方を持っています。異なる経験や価値観を持った者がコミュニケーションをとるのは、なかなか簡単ではありません。
上司が若い新入社員の話を聞く際は聴き手になり、対話することを意識しましょう。新入社員の声を理解し、受け入れることが新入社員の成長を促進する第一歩となります。
ポジティブな質問で発言を促す
新入社員の主体性を引き出すには、単なる質問ではなくポジティブな質問で発言を促すことが大切です。
質問の際に、ネガティブな質問ばかりでは新入社員の意欲を損ないかねません。「現状で改善要素がある部分はどこだと思うか」「今以上の結果を出すためにはどのようなアイデアがあるか」といったポジティブな質問を通じて、新入社員が自己表現できる状況を作り出すことが重要です。
また、漠然とした質問では回答が難しくなります。上司は、質問の方向性やポイントを明確にしつつ、新入社員が自ら考えて発言できる質問を投げかけることを意識しましょう。
具体的なアドバイスをする
新入社員の主体性を引き出すには、具体的なアドバイスが重要です。若い新入社員は、抽象的な指針や精神論よりも、具体的なステップや行動の方が理解しやすい傾向にあります。アドバイスを新入社員の成長に結びつけるためには、上司が業務の指示や指導でいかに具体性を持たせられるかが大切です。
具体的なアドバイスは、協力して成長する環境の構築にも繋がります。抽象的な言葉よりも、具体的なスキルや課題に焦点を当て、「ここを改善すると成果が上がる」「この方法で課題にアプローチすると○○に効果的だ」といった形でアドバイスをするよう心がけましょう。
業務権限・裁量を与える
先述の通り、業務権限と裁量を積極的に与えることも、新入社員の主体性を引き出すために重要なポイントです。
新入社員のスキルや経験に合わせて段階的に業務を任せてみましょう。上司のサポートだけでなく、新入社員に「上司に仕事を任された」という意識を持たせることで、自分の仕事に対する責任感を育成します。
また新入社員の成長に伴い、業務権限や担当範囲を徐々に広げることも大切です。新入社員の成果や挑戦意欲を考慮し、複雑な業務やプロジェクトを任せることで、新入社員へ負担をかけずに主体性を引き出すことに繋がります。
成功体験を積ませて自信を付けさせる
「成功体験を積ませて自信をつけさせる」ことも、新入社員の主体性を引き出す方法の一つです。
簡単で具体的な業務からスタートさせ、仕事を通じて成果を上げた際には、成功を認め、評価することが大切です。成功体験や評価を通して、新入社員は自分の能力に対する自信をつけ、次第に挑戦的な業務にも前向きに取り組むようになります。
このとき、成果や成績に応じて徐々に責任を委ねていくことが鍵です。成功体験が増え、自信をつけた新入社員は、自分のスキルやアイデアを活かして組織に貢献できていることを実感でき、やる気を持続させることができます。
放置せずサポートを怠らない
新入社員の主体性を引き出すためには、新入社員を放置せずサポートを行いましょう。
新入社員を「気にかけている」だけではなく、成果や行動に対して積極的で具体的なサポートが重要です。成長に必要な知識を共有したり小まめにフィードバックを行ったりすることで、新入社員は自分の強みや改善点を理解し主体的に業務へ取り組む姿勢になります。
また、上司は定期的な対話をこころがけましょう。新入社員が抱える課題や目標が共有出来れば、より適切なサポートが可能です。
まとめ
本記事では、新入社員の受け身な姿勢を変える方法に焦点を当て、NGな指導と主体性の引き出し方を解説しました。主体性を引き出すには、上司がイマドキの新入社員の特徴や価値観を理解して、成長する機会を設けることが重要といえます。
資料ダウンロード
超実践型!ビジネススキル研修(マルチタスク処理・優先順位付け研修)
ワークハピネスの新入社員研修ラインナップ
新入社員向けのスキル研修やマインド研修をご用意しています。
お気軽にお問い合わせください。

大学卒業後、外資系医療機器メーカーで営業に従事。
6年間で8人の上司のマネジメントを経験し、「マネジャー次第で組織は変わる」と確信し、キャリアチェンジを決意する。
2009年にワークハピネスに参画し、チェンジ・エージェントとなる。
医療メーカーや住宅メーカーをはじめ、主に大企業の案件を得意とする。また、新人から管理職まで幅広い研修に対応。
営業、営業企画、新人コンサルタント教育を担当後、マーケティング責任者となる。
一度ワークハピネスを退職したが、2021年から復帰し、当社初の出戻り社員となる。現在は、執行役員 マーケティング本部長。