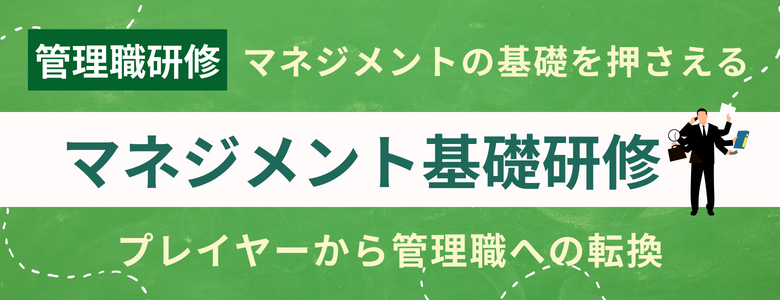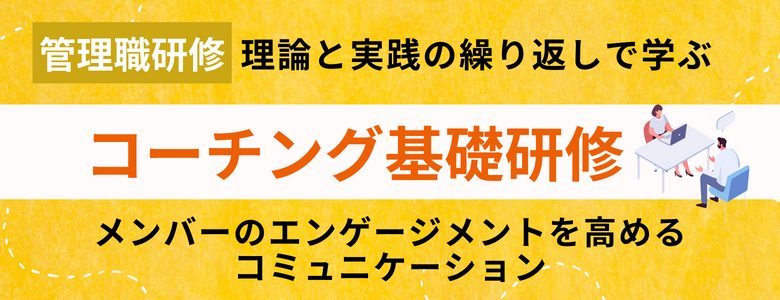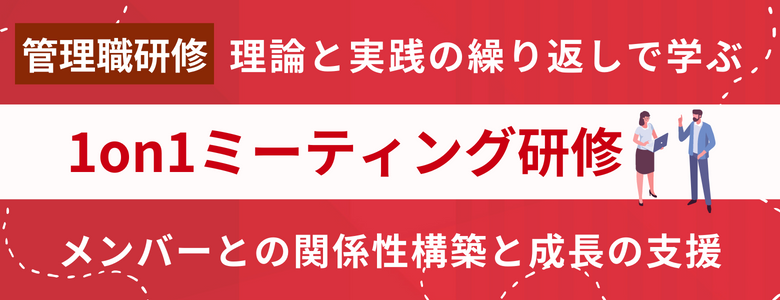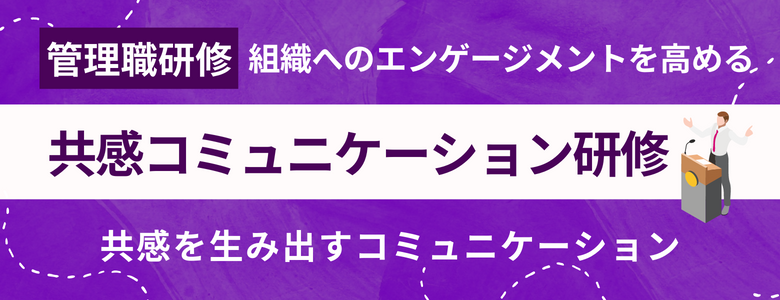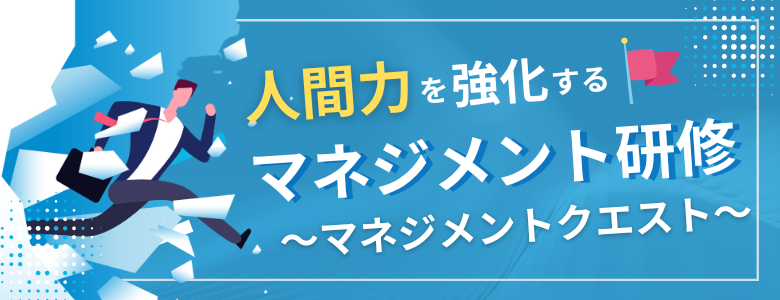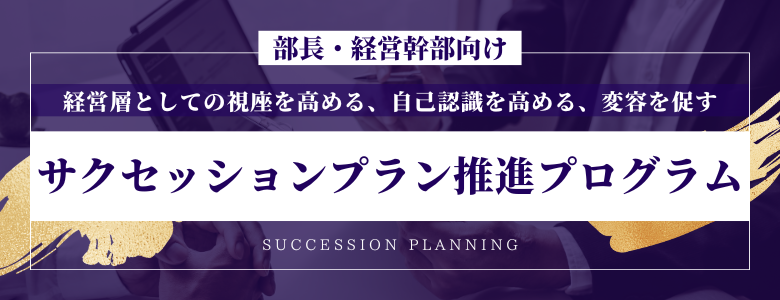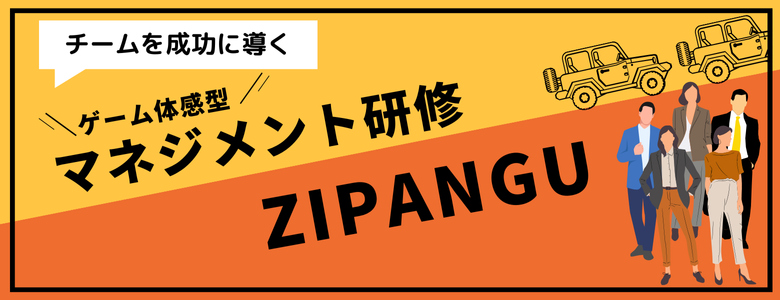課長研修とは?目的・内容・テーマ・レポート例まで徹底解説【2025年最新版】
課長研修は、組織の“中核”を担う管理職が、チーム成果を最大化するために欠かせないステップです。
現場と経営をつなぐ課長層には、マネジメント力・育成力・戦略実行力といった多面的なスキルが求められます。
一方で「どんな研修を受ければよいのか」「研修後のレポートはどう書けばいいのか」など、疑問を持つ方も多いでしょう。本記事では、課長研修の目的や内容、テーマ別のカリキュラム例から、感想・レポートの書き方、選び方のポイントまでをわかりやすく解説します。
新任課長・課長補佐・営業課長・行政職など、あらゆる立場に対応できる「実践的な研修理解ガイド」としてご活用ください。
課長研修とは? ― 役割・位置づけから理解

企業の中核を担う「課長」は、現場と経営層をつなぐ重要なポジションです。部下育成・チーム成果の最大化・経営方針の実行といった多様な役割を担うため、課長に求められる能力は年々高度化しています。
本記事では、課長という職位の位置づけから、なぜ課長研修が求められるのか、そして研修を通じて期待される効果までを体系的に解説します。
「課長」とはどのような職位か
課長は、組織の中間管理職として「現場の統率」と「経営戦略の実行」を担う職位です。
一般的に、課長の主な役割は以下の3点に整理できます。
- チームマネジメント
部下の育成・目標設定・進捗管理を通じて、チーム全体の成果を最大化します。単なる管理者ではなく、メンバーの能力を引き出す「リーダーシップ」が求められます。 - 業務遂行・改善責任
日々の業務を効率的に遂行しながら、課題発見・改善提案を行い、現場の生産性向上を推進します。経営層の方針を理解し、現場に落とし込む役割も重要です。 - 経営と現場の橋渡し役
経営側が描くビジョンを現場に浸透させると同時に、現場の課題を経営にフィードバックする“双方向の調整役”として機能します。
こうした背景から、課長は「プレイヤーからマネジャーへの転換期」にある人材が多く、技術力だけでなくマネジメント力・人間関係構築力・戦略思考が必要とされるポジションです。
なぜ「課長研修」が求められるのか(背景・課題)
かつての課長は「経験と勘」で部下を導く時代もありましたが、現代の企業環境ではそれだけでは通用しません。
課長研修が必要とされる背景には、以下のような構造的課題があります。
1. 中間管理職へのプレッシャー増加
経営からは成果を求められ、部下からは心理的安全性や働きやすさを求められる。双方の板挟みになることで、メンタル的負荷や燃え尽き症候群に陥る課長も少なくありません。
2. 部下育成力の不足
若手社員の価値観の多様化や、リモートワークによるコミュニケーションの減少により、「育て方がわからない」と悩む課長が増えています。
研修を通じて、1on1・フィードバック・コーチングといった現代的マネジメント手法を習得する必要があります。
3. 戦略実行の要となるポジション
DX推進や業務変革を現場で実行するのは、まさに課長クラスの管理職です。経営層の方針を理解し、チームを巻き込みながら推進する“変革リーダー”としてのスキル強化が不可欠です。
このように、「課長研修」は単なる昇進者向けの教育ではなく、組織の変革と持続的成長のカギを握る育成施策として位置づけられています。
課長研修の目的・期待される効果
課長研修の目的は、「マネジメント層としての自覚とスキルを体系的に身につけること」です。
多くの企業では、以下の3つの目的を中心に設計されています。
1. マネジメントスキルの強化
- 部下の目標設定・評価・育成
- チームのモチベーション管理
- 問題解決・意思決定プロセスの標準化
これらを通じて、再現性の高いマネジメントを習得します。
2. リーダーシップの確立
「上司だから」ではなく「信頼されるリーダー」としての在り方を学ぶことが目的です。セルフマネジメント・EQ(感情知能)・心理的安全性など、現代的リーダーシップの基礎を理解します。
3. 組織視点・経営視点の醸成
現場課題だけでなく、会社全体の戦略や数字を意識した意思決定を行う力を育てます。
「自部署の最適化」から「全社の最適化」へと視座を高めることが、経営人材育成の第一歩です。
4. 課長研修の期待される効果(成果例)
- チームの生産性・目標達成率の向上
- 部下との信頼関係強化・離職率の低下
- 業務改善・提案件数の増加
- 上層部との報連相の質の向上
- 自己理解・セルフリーダーシップの深化
課長研修を通じて、個人の成長だけでなく組織全体のエンゲージメント向上や次世代管理職の育成基盤強化にもつながります。
課長研修の内容・テーマ(カリキュラム例)
課長研修は、単なる知識習得の場ではなく、「現場を動かすリーダー」へと成長するための実践型プログラムです。
企業規模や業種によって内容は異なりますが、共通して重視されるのはマネジメント力・人材育成力・リーダーシップの確立です。
ここでは、一般的な課長研修の構成とテーマ例を体系的に解説します。
課長研修の基本カリキュラム構成(1日〜数日)
課長研修は、目的や到達レベルに応じて1日集中型〜3日間程度の短期集中コースが多く見られます。
以下は、代表的なカリキュラム構成の一例です。
| 日程 | 主な内容 | 学習目的 |
|---|---|---|
| 1日目 | 役割理解・マネジメント基礎 | 課長としての立場・責任を再確認する |
| 2日目 | 部下育成・コミュニケーション | 指導力・面談力・目標管理の実践方法を学ぶ |
| 3日目 | チーム運営・問題解決 | 実践ワークを通じて現場への落とし込みを行う |
| フォローアップ | 振り返り・アクションプラン共有 | 学んだ内容を業務に定着させる |
企業によっては、事前課題(マネジメント診断・部下評価)や研修後フォロー面談を組み合わせ、PDCA型の成長支援サイクルを設計するケースも増えています。
課長研修の主な研修テーマ一覧
課長研修では、役職として求められるスキルセットを体系的に強化するため、以下のようなテーマが設定されます。
1. マネジメント・リーダーシップ
- 課長の役割と責任
- リーダーシップスタイル診断
- チームビルディングと心理的安全性の確保
→ 経営方針を現場に浸透させる「組織運営力」を養成します。
2. 部下育成・目標管理・業務改善
- 目標設定と評価面談の進め方(MBO・OKR)
- コーチング/ティーチングの使い分け
- OJT・人材育成計画の設計方法
- 業務改善・生産性向上の手法(PDCA・カイゼン)
→ 人を動かす・育てる「成果マネジメント力」を磨きます。
3. コミュニケーション・リスク管理
- 上司・部下・他部署との信頼構築
- 伝え方・傾聴力・アサーション
- ハラスメント防止・メンタルケア
- 予防型リスクマネジメント・コンプライアンス意識
→ 人間関係と組織安定の基盤を強化します。
これらのテーマを総合的に学ぶことで、課長としての「判断力・統率力・育成力」がバランスよく向上します。
課長研修テーマ別コース紹介・おすすめプログラム例
課長研修は、目的別に特化したコースを選択できるケースも多くあります。
代表的なプログラム例を以下に紹介します。
| コース名 | 主な内容 | こんな課長におすすめ |
|---|---|---|
| リーダーシップ革新コース | 組織ビジョンの共有/信頼構築/モチベーションマネジメント | 新任課長・チームリーダー層 |
| 部下育成・1on1強化コース | 面談スキル・コーチング・評価制度運用 | 育成に課題を感じている中堅課長 |
| 業務改善・組織変革推進コース | 現場課題抽出・改善PDCA・変革事例共有 | 生産性や効率化を求められる管理職 |
| 心理的安全性とハラスメント対策コース | 組織文化づくり・対話力・リスク管理 | チーム内トラブルを防ぎたい管理者 |
| 次世代経営人材育成コース | 経営指標・戦略思考・数値管理 | 将来の部長・経営候補クラス |
こうしたプログラムを組み合わせることで、個人課題と×組織課題の両面からマネジメント力を伸ばす設計が可能です。
実践型・塾型・課長クラス研修の特徴
● 実践型研修
ロールプレイ・ケーススタディ・グループワークを中心に、現場の実例をもとに学ぶ形式で実施されます。
「知識で終わらせず、行動変容を起こす」ことを目的とします。
→ 研修翌日から使えるスキル定着率が高いのが特徴です。
● 塾型研修
少人数制で長期的に実施し、講師・メンターが個別フィードバックを行う形式。
受講者同士のディスカッションを通じて他業界の視点や自己内省力を高めます。
● 課長クラス専門研修
部長候補層を見据え、戦略的思考・数値管理・部門運営などを扱う上級コース。
管理職としての意思決定・チーム経営力を磨き、経営層との共通言語を習得します。
課長研修後フォロー・定着支援の仕組み
課長研修の効果を持続させるには、「受講後の定着支援」が欠かせません。
多くの企業では以下のような仕組みを導入しています。
- フォローアップ研修(1〜3ヶ月後):実践事例を共有し、改善策を議論
- 上司・人事との面談制度:研修内容を業務評価と連動
- eラーニング・オンラインサロン:復習・最新情報の継続学習
- 社内プロジェクト参加型制度:実務でスキルを発揮する場を設ける
これにより、「研修で終わる」ではなく「行動が変わる・成果につながる」課長育成が実現します。
課長研修の選び方・おすすめポイント

課長研修は、「どの課題を解決したいか」「どんな層に実施するか」によって選び方が大きく変わります。
近年では、対面・オンライン・英語対応など多様な形式が登場し、目的に合った研修を選ぶことが成果につながる重要なポイントです。
ここでは、失敗しない課長研修の選び方と、対象別・形式別のおすすめポイントを解説します。
課長研修を選ぶ際のチェックポイント
課長研修を比較・検討する際は、以下の観点を押さえておくと効果的です。
1. 目的・課題を明確にする
「昇格者のマネジメント力を育てたい」「既存課長の育成手法を強化したい」など、研修目的を具体化することが最初のステップです。
目的が曖昧だと、講師やカリキュラム選定が形骸化しやすくなります。
2. 現場に活かせる実践性
理論だけで終わらず、ロールプレイ・ケーススタディなど実践型カリキュラムを重視しましょう。
現場課題に即した内容であれば、研修後の行動変容やチーム成果につながりやすくなります。
3. 講師の専門性・業界理解
マネジメント経験や人材育成実績を持つ講師が担当する研修を選ぶことが理想です。
特に業界特性を理解している講師は、より具体的で共感性の高い指導が可能です。
4. フォローアップ体制
研修効果を定着させるために、研修後面談・オンライン復習・アクションプラン共有などのフォロー制度が整っているか確認しましょう。
「受けて終わり」ではなく、「現場に根付く」研修が評価されています。
5. 受講者層とレベルの適合
新任課長向け・既存課長向け・補佐層など、参加者の立場や経験値に合わせた難易度設定が重要です。
混在型では理解度に差が出やすいため、層別に最適化された研修が望ましいでしょう。
課長研修の対象別おすすめ(新任/既存/補佐/営業/行政)
課長研修は、対象層によって重点ポイントが異なります。
以下に代表的な分類とおすすめテーマをまとめます。
| 対象層 | 主な目的・課題 | おすすめテーマ・内容例 |
|---|---|---|
| 新任課長 | 管理職としての意識転換・部下育成の基本習得 | リーダーシップ基礎/1on1/報連相マネジメント/初めての評価面談 |
| 既存課長 | チームの成果最大化・後進育成・業務改善 | 問題解決力/コーチング/戦略的マネジメント/心理的安全性 |
| 課長補佐・代理 | 将来の課長候補としてのスキル育成 | マネジメント準備講座/役割理解/目標設定とフォロワーシップ |
| 営業課長 | 営業戦略・数字管理・部下同行指導 | KPIマネジメント/成果型リーダーシップ/営業プロセス改善 |
| 行政・公的機関課長 | 公務員組織でのチーム統率・住民対応 | 公務員倫理・組織統率・コミュニケーション研修・ハラスメント防止 |
このように、「役割」「課題」「業務特性」に合わせてカスタマイズすることで、より効果的な課長研修を設計できます。
課長研修形式別(対面・オンライン・英語対応など)
働き方の多様化に伴い、課長研修の形式も柔軟に選べるようになっています。
それぞれのメリット・適性を理解して選びましょう。
● 対面研修
- 特徴:グループワークや実践ロールプレイが中心。臨場感と一体感が得やすい。
- おすすめ:新任課長やチームマネジメント系のテーマ。対話・体感重視の内容に最適。
● オンライン研修
- 特徴:全国拠点やリモートワーク環境でも受講可能。録画・復習も容易。
- おすすめ:既存課長の継続学習や、業務改善・リーダーシップ理論など。
- ポイント:双方向コミュニケーション機能(ブレイクアウトルーム・チャット討論など)があると効果的。
● ハイブリッド研修(対面+オンライン)
- 特徴:現場参加とリモート参加を組み合わせ、全国規模の組織にも対応。
- おすすめ:企業全体の階層別研修や、複数拠点の連携を要するケース。
● 英語・グローバル対応研修
- 特徴:海外拠点や外国籍スタッフを含むチーム運営を想定したプログラム。
- 内容例:Global Mindset / Diversity & Inclusion / Cross-cultural Leadership
- おすすめ層:グローバル企業の中間管理職、海外出向・連携部門の課長層。
課長研修の社内共有・フォローアップの方法
レポート提出後に大切なのが、「研修を現場でどう生かすか」です。
以下のようなフォローアップ体制を整えることで、学びが組織に定着します。
1. 上司・人事への共有
提出後、上司との面談で「実践計画」を共有することで、サポートや評価につながります。
例:
「次回の評価面談では、チーム目標設定の仕方を見直す予定です」
このように宣言すると、上司も進捗フォローしやすくなります。
2. チーム内への共有会
課長自身が学んだ内容をチームミーティングで共有することで、組織全体の成長機会に。
- 「心理的安全性を高めるための言葉がけ」
- 「フィードバック面談の実施方法」
など、実務につながるテーマを抜粋して伝えるのが効果的です。
3. 振り返り・実践記録の作成
1〜3ヶ月後に「学びの実践結果」を簡易レポートとして記録。
例:
- 実践した内容
- 改善できた点・課題点
- 次のアクション
このPDCAサイクルを回すことで、研修が単発ではなく“育成文化”として根付きます。
課長研修でよくある課題と改善策
課長研修は多くの企業で実施されていますが、「研修を受けたのに現場が変わらない」「一時的な意識変化で終わる」といった悩みも少なくありません。
課長層は企業の中核を担う重要なポジションである一方、実務とマネジメントの両立に苦労する層でもあります。
本記事では、課長研修が効果につながらない主な原因と、成果を出すための改善ポイントを詳しく解説します。
研修が効果につながらない主な原因
せっかく時間とコストをかけて実施した課長研修も、実務に活かされなければ意味がありません。
多くの企業が直面する「効果が出ない理由」は、以下のような構造的課題にあります。
1. 目的が不明確なまま実施している
「とりあえず毎年恒例で実施」「昇進者には必須だから」といった理由で行うと、受講者の主体性が生まれません。
課長層にとっての課題(部下育成・チーム改善・経営視点など)を明確に設定し、研修の目的と期待成果を共有することが重要です。
2. 現場との乖離がある
現場の実情と合わない理論中心の内容では、「実際の職場では使えない」と感じられがちです。
特に課長層は多忙であり、即効性のある実践スキルを求める傾向があります。
事前に課題ヒアリングやケース収集を行い、「現場に即した設計」が必要です。
3. 研修後のフォローが不足している
「受けたまま放置」では行動変容が起きません。
研修直後はモチベーションが高くても、1〜2ヶ月後には元の行動に戻ることが多いです。
上司面談・オンライン振り返り・アクションプラン報告などの仕組みを設けることで、実践と改善を促せます。
4. 評価制度・組織文化が支援していない
研修で新しいマネジメントスタイルを学んでも、会社全体が「変化を許容しない文化」だと定着しません。
学びを活かすためには、経営層の理解・制度面での後押しも欠かせません。
課長層が抱える典型的な課題
課長層は、経営と現場の両方からプレッシャーを受ける“板挟みポジション”です。
以下に、代表的な課題と背景を整理します。
| 課題 | 背景・原因 | 具体例 |
|---|---|---|
| 部下育成が進まない | 若手の価値観多様化、教え方の難化 | 「指示しても動かない」「考えさせる指導が苦手」 |
| チームマネジメントが属人的 | 自己流マネジメント・経験頼り | 「感覚的に指導」「数字だけで評価」 |
| 上層とのコミュニケーション不足 | 経営視点・数字理解の不足 | 「報告が遅れる」「戦略と日常業務のズレ」 |
| 業務負荷が高く時間管理が困難 | プレイングマネジャー化 | 「自分の仕事が多すぎて育成まで手が回らない」 |
| 変化への抵抗・メンタル疲労 | DX・組織再編・人員削減など環境変化 | 「部下より自分が不安」「変化対応に消耗」 |
これらの課題を解消するには、「意識・スキル・仕組み」の3層でアプローチする必要があります。
成果を出すための改善ポイント
課長研修を“受けただけで終わらせない”ためには、次の3つの改善ポイントを押さえることが重要です。
1. 個別課題に合わせた設計
研修テーマを「全員一律」ではなく、個人・部門の課題別にカスタマイズすることで効果が高まります。
たとえば:
- 育成力が弱い → コーチング・1on1強化コース
- 数字管理に課題 → 戦略思考・経営指標理解コース
- チーム内不和 → コミュニケーション・心理的安全性研修
2. 実践・振り返りを組み合わせる
研修内で「学び→実践→共有→再改善」のサイクルを組み込むと、定着率が向上します。
具体的には:
- 研修内で現場課題を題材にしたケースワークを実施
- 終了後1〜3ヶ月でフォローアップ面談
- 成果共有会で他部署の成功事例を学ぶ
こうした循環型設計により、学びが行動に変わる仕組みを作れます。
3. 組織ぐるみのサポート体制
人事・上司・経営層が連携し、研修後の行動を見守る仕組みを持つことが成功の鍵です。
たとえば:
- 研修後レポートを人事がレビューし、評価面談に反映
- 経営層が研修内容を理解し、現場変革を支援
- 定期的な「管理職ラウンドテーブル」で課長同士の学び合いを促進
このように「個人努力+組織支援」をセットで行うことが、研修成果を持続させるポイントです。
キーワード別:課長研修の種類・特徴まとめ
課長研修には、受講対象・目的・形式によってさまざまな種類があります。
「新任課長向け」「課長補佐向け」「営業課長研修」など、階層・職種・テーマごとにカリキュラムが異なり、目的に合わせて最適なプログラムを選ぶことが重要です。
ここでは、代表的な課長研修の種類と特徴をキーワード別にまとめて紹介します。
新任課長研修/目的・レポート例
特徴・目的
新任課長研修は、プレイヤーからマネジャーへ転換するための意識変革を目的とした研修です。
昇進直後の「マネジメント未経験層」に向け、課長の役割理解・部下育成・目標管理などを体系的に学びます。
主な内容
- 課長としての役割・責任
- 部下との関わり方(1on1・評価・フィードバック)
- チームマネジメントの基本
- 経営層とのコミュニケーション・報連相スキル
レポート例(抜粋)
「自分の成果ではなく“部下の成果で評価される立場”に変わったことを実感した。
今後は指示ではなく“質問で導く”リーダーを意識して行動する。」
課長補佐研修/感想・レポート
特徴・目的
課長補佐研修(または課長代理研修)は、次期課長候補やサブリーダー層を対象にしたステップアップ型の研修です。
課長職を補佐しながら、組織運営の理解・フォロワーシップ・育成補助スキルを磨きます。
主な内容
- 上司(課長)との協働・支援方法
- チーム運営のサブマネジメント
- 問題発見力・提案力の強化
- リーダー補佐としての心理的サポート
感想例
「課長の視点を知ることで、自分の発言や判断の責任を意識するようになった。
フォローだけでなく、“支えるリーダー”として行動を変えたい。」
課長クラス・課長級・部課長研修
特徴・目的
中堅以上の管理職層を対象とした「課長級」または「部課長合同研修」は、戦略実行力と組織変革力を養う中上級コースです。
複数部署を統括する立場としての視座・意思決定力・数字理解を強化します。
主な内容
- 経営方針の理解と現場実装
- KPI/KGIの設定と運用
- 部下マネジメントから部門マネジメントへ
- 事業計画・予算策定・部下のキャリア支援
この層は、部下育成だけでなく次世代管理職の育成責任を担う立場としての自覚が求められます。
マネジメント革新コース・課長塾研修
特徴・目的
「マネジメント革新コース」や「課長塾研修」は、**中長期で行動変革を促す“実践型プログラム”**です。
集合研修に加え、ケース討議・メンター面談・アクションプラン発表などを通じて、実務で成果を出す力を磨きます。
主な内容
- 自己マネジメント・セルフリーダーシップ
- 部門間連携・組織横断プロジェクト推進
- 人間関係構築・ファシリテーション
- 自身のリーダー像確立
特徴的なスタイル
- 少人数・塾形式で「学び合い」「内省」を重視
- 研修後も定期フォローを行い、継続的成長を支援
英語対応課長研修
英語対応課長研修(Global Manager向け)
- Global Mindset研修:異文化理解・グローバルチーム運営
- Cross-cultural Leadership:海外拠点マネジメント力向上
- Business Communication in English:外国人部下への指導・報連相スキル
グローバル企業や外資系企業では、英語対応のマネジメント研修を通じて「多国籍チーム運営力」を磨くケースが増えています。
郵便局課長・課長代理・選抜研修
特徴・目的
郵便局などの公共・準公務系組織では、課長・課長代理・選抜職員向けの研修制度が体系化されています。
一般企業と異なり、組織倫理・住民対応・安全管理などの“公共責任”を重視した内容が特徴です。
主なテーマ
- コンプライアンス・リスクマネジメント
- チーム統率と人材指導
- 地域貢献意識と組織理念の浸透
- 部下・顧客対応における危機管理
「選抜課長研修」では、上位職登用を見据えた評価型プログラムが実施され、リーダー資質・判断力・統率力が総合的に評価されます。
営業課長研修・実践研修
営業課長研修の特徴
営業課長は、「売上責任」と「部下育成責任」を同時に負う立場です。
そのため、数字管理と人材マネジメントを両立する実践的研修が中心となります。
主な内容
- 営業戦略立案・KPIマネジメント
- 営業プロセス分析・改善
- 部下同行指導・モチベーション管理
- 成果面談・表彰文化の構築
営業課長研修は、「数字を上げるマネジメント」を科学的に体系化する点が特徴です。
課長研修で成果を上げる3つのポイント
課長研修を真に成果につなげるためには、「受けること」よりも「活かすこと」が重要です。
多くの企業で共通して成果を出している組織には、次の3つのポイントがあります。
① 目的を明確にし、現場課題に直結させる
研修は“形式的な教育”ではなく、“組織課題の解決手段”として設計することが大切です。
「何を解決したいのか」「どの行動を変えたいのか」を明確にし、現場に即したテーマを設定しましょう。
② 学びを行動に変える仕組みをつくる
研修後のフォローアップやアクションプラン共有など、実践→振り返り→改善のサイクルを組み込むことで、行動変容が定着します。
個人の努力任せではなく、上司・人事・経営が連携して支援する体制が成果を左右します。
③ 継続的な育成文化を根づかせる
単発の研修ではなく、課長層が常に学び・成長し続ける「学習する組織文化」を育むことが重要です。
たとえば、社内勉強会・リーダー座談会・マネジメント塾など、継続学習の仕組みを整えることで、組織全体の底上げが可能になります。
課長は、現場と経営をつなぐ“組織の心臓部”です。
課長研修を通じて学んだ知識や気づきを行動に変え、チームの成果・人材育成・組織文化を支えるリーダーとして成長していくことが、企業の持続的成長のカギとなります。
ワークハピネスでのマネジメント研修
ワークハピネスでは「管理職としての役割がしっかり果たされていない」「マネジメントに関する教育ができていなかった」「メンバーへの動機づけができていない」などの課題に対応した、基礎的なマネジメント研修を実施しています。
マネジメント研修のゴールは、マネジメントに関する認識が統一されること、コミュニケーション力&マネージャーに必要なスキルの習得です。
ワークハピネスのマネジメント研修メニュー
ワークハピネスの研修メニューの全体像や実績はこちら

大学卒業後、外資系医療機器メーカーで営業に従事。
6年間で8人の上司のマネジメントを経験し、「マネジャー次第で組織は変わる」と確信し、キャリアチェンジを決意する。
2009年にワークハピネスに参画し、チェンジ・エージェントとなる。
医療メーカーや住宅メーカーをはじめ、主に大企業の案件を得意とする。また、新人から管理職まで幅広い研修に対応。
営業、営業企画、新人コンサルタント教育を担当後、マーケティング責任者となる。
一度ワークハピネスを退職したが、2021年から復帰し、当社初の出戻り社員となる。現在は、執行役員 マーケティング本部長。